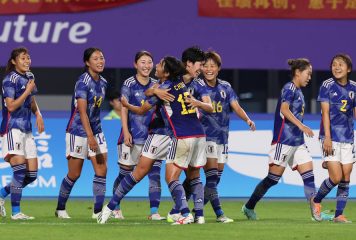サッカー大国・ブラジルの“ドリームチーム” 特有の芸術性に富んだスタイルを築いた“過去の名将”テレ・サンターナとは?

【カメラマンの目】W杯のタイトルは手にせずとも、観客を魅了したブラジルらしいチーム作りに再注目
サッカー大国ブラジルのヒエラルキーのトップに位置するセレソン(ブラジル代表の愛称)は、ワールドカップ優勝最多の5回を誇り、どんな時代にあっても世界のサッカーシーンで注目されてきた存在である。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
しかし、チーム内に目を向ければ、自らの才能に絶対の自信を持つ選手たちは個性派揃いで、彼らをひとつに纏め上げる作業を行う指揮官の仕事は並大抵の難しさではない。なにも選手たちを納得させられる戦術理論と指導方法を身に付けていれば、セレソンの監督が務まるというものでもないのだ。
選手たちに一目置かれるような人格者であることが望まれ、勝利への期待度も高いサポーターからのプレッシャーにも屈しない強い精神力も持ち合わせている必要がある。しかも、母国のサッカーが世界一だと自負する国民が求めるものは、勝利だけに留まらず、攻撃的で芸術性に富んだ他のどんな国もマネのできない至高のサッカーだ。
だが、結果としての勝利と内容の美しさを同時に満たすことは簡単なことではない。まして、情報化社会となり相手の研究が容易となった現代サッカーでは、相手を結果と内容で圧倒することは難しく、ブラジルの指揮官であっても“攻撃”と“守備”、あるいは“個人技”と“チーム戦術”のどれを重視するかで、セレソンといえどもチームの特徴は変わり、人々の期待に応えるサッカーを必ずしも展開できるとは限らない。
さまざまな人々の思いやチーム内の力学が交差するセレソンを取り巻く環境に、歴代の監督たちはどう向き合ってきたのか。カメラのファインダーを通して見た彼らの目指したスタイルや人間像を6回に渡って紹介していく。
フェンス越しにサポーターから差し出されるシャツや用紙にサインをしているのは、ブラジルの名将テレ・サンターナである。膨大なポジフィルムのなかから切り取られたこの1枚は、テレ・サンターナがブラジルのサンパウロFCを率いていたときのもので、正確な日付を特定することはできなかったが1994年に撮影した写真だ。
当時のサッカー界の情勢は、スター選手の多くがヨーロッパ大陸の主要リーグのクラブでプレーする一極集中の時代へと向かいつつあった。その波はサッカー王国ブラジルのリーグにも到達し、スター選手の海外クラブ移籍の流れは加速の一途を辿っていくことになる。それでも90年代前半は変貌していく時代の境界線にあり、国内にはまだクラッキ(名手)と呼べるスター選手が残っていた。
練習後、テレ・サンターナは選手たちと同じく、いや彼ら以上にサポーターからサインを求められていた。サインをしてもらうために差し出されている品々の多さから、サンパウロを南米屈指の強豪へと仕立て上げたテレ・サンターナの存在が、サポーターにとっていかに絶大だったかが見て取れる。

サンパウロ時代、トレーニングセンターの敷地内に住んでいた
テレ・サンターナに率いられたサンパウロは、南米王者と欧州チャンピオンが冬の東京で対戦するトヨタカップの舞台で、92年にFCバルセロナ、93年にはACミランと試合を行っている。結果は2連続でヨーロッパチームに勝利し優勝を果たしている。
ここにヨハン・クライフ率いるバルセロナとの対戦で、サンパウロの通訳を務めていた方から聞いた逸話がある。試合前に円陣を組むとキャプテンのライー(94年ワールドカップ・アメリカ大会メンバー)は仲間の選手たちに向かって、試合には自分たちも勝ちたいが相手だって勝ちたい。しかし、俺たちのこの友情と団結力はどんなチームにも負けないと語ってチームを鼓舞していたそうだ。そして、サンパウロはフリスト・ストイチコフに先制点を許したものの、勝利へと向かう団結力を失うことなくライーの2得点で逆転勝利を収めることになる。
そうしたチームの一体感を生んでいたのは、指揮官の行動を知れば納得できる。驚くことに当時のテレ・サンターナは、サンパウロのトレーニングセンターの敷地内に住んでいたのだ。
監督生活も終盤となり、その道を究めた結果、導き出されたのが四六時中サッカーに接することだったわけだ。言うまでもなく選手との関係は深まる。トップのプロだけでなくユースなどにも目を配り、チームの構築と強化に励むテレ・サンターナを先導者にサンパウロという組織は纏まっていた。
テレ・サンターナの優れた点は選手の特徴を的確に見抜き、チーム状況において独自の起用法を展開する決断力にある。たとえば右サイドバック(SB)の選手としてイメージが強いカフー(2002年W杯日韓大会のキャプテン)を92年のトヨタカップでの試合もそうであったように、引き続き93年のチームでも背番号11番のフォワード(FW)として起用している。

カフーは元々攻撃の選手だったが、サンパウロに入団するとSBへとコンバートされていた。豊富な運動量と相手守備網を突破する鋭い推進力を誇り、右サイドでのプレーならどのポジションでもこなす能力を持ったオールラウンダーであり、同時期での代表ではDFの選手として評価されプレーしていた。そのカフーをテレ・サンターナはクラブではより攻撃で力を発揮する右サイドの最前列で起用している。
そして、翌年には右サイドの最後列へとポジションを戻している。同じ94年ではSBを主戦場としてプレーしていたレオナルド(のちに鹿島アントラーズでプレー)に、エースナンバー10番とともにゲームメーカーの仕事を託している。
自ら選手の能力を判断し、ときに選手に新たな役割を与え、より力を発揮させる。選手の才能を存分に解放させ、チームを強力な集団へと作り上げるテレ・サンターナだが、そのスタイルがもっとも表現されたのが代表の舞台だった。
82年と86年のW杯でブラジル代表を指揮
テレ・サンターナは82年と86年のW杯でブラジル代表を指揮している。特に82年のW杯を戦ったセレソンは、栄光のブラジルサッカー史に燦然と輝く、いまでも語り草となっている夢のチームであった。
なんといっても注目されたのは中盤である。ゲームメイクを担いエースナンバー10を背負うジーコ、チームの精神的支柱のキャプテン・ソクラテス、ブラジル的テクニックと欧州的体力を兼ね備えたパウロ・ロベルト・ファルカン、そしてこの3人を後方から支えるボランチのトニーニョ・セレーゾが形成する中盤は黄金のカルテットと称されるほど魅力に溢れていた。
強烈な個性を持った選手はこの4人に限らず、他にも左右のSBにはジュニオールとレアンドロという高い攻撃力を持った選手がレギュラーを務めていた。さらに黄金の4人がチャンスと見れば積極的に前線へと進出するため、強シューターとして名を売った左ウイングのエデルは前線に張るのではなく、中盤でプレーすることもあった。
カナリアの精鋭たちによる華麗な個人技と、足元から足元へとボールをつなぐ正確無比なパスワークを駆使したアタッキングサッカーは、当然ながら見る者を魅了した。GKと中央の守備を担う2人以外はポジションにこだわらず臨機応変にプレーし、最大限に引き出された選手たちのパワーを攻撃へと注ぐ、テレ・サンターナが目指したスタイルの究極が82年のブラジルだった。
なによりテレ・サンターナはブラジルサッカーの本流を突き進む精神を貫いていた。相手の牙城を高度なテクニックを持って攻略する、まさに比類なき美的表現へと到達したサッカーは、王国を自負する国民が求めていた、これぞブラジルというスタイルだった。
ただ、テレ・サンターナはワールドカップ(W杯)の優勝カップを手にしてはいない。観衆の心を熱くさせるチームを作りながらも、必ずしも結果が合致しないところにサッカーの難しさがある。
しかし、テレ・サンターナは選手の才能を引き出す起用と、監督生活終盤にはトレーニング施設で生活を送るサッカーへの飽くなき追及と情熱によって、至高のチームを作り上げた名将としてブラジル国民の心に深く刻まれている。セレソンを率いた歴代の監督のなかでも、人々が王国ブラジルを真っ先にイメージする攻撃的で芸術性に富んだスタイルをピッチで表現した指揮官であった。
(徳原隆元 / Takamoto Tokuhara)
徳原隆元
とくはら・たかもと/1970年東京生まれ。22歳の時からブラジルサッカーを取材。現在も日本国内、海外で“サッカーのある場面”を撮影している。好きな選手はミッシェル・プラティニとパウロ・ロベルト・ファルカン。1980年代の単純にサッカーの上手い選手が当たり前のようにピッチで輝けた時代のサッカーが今も好き。日本スポーツプレス協会、国際スポーツプレス協会会員。