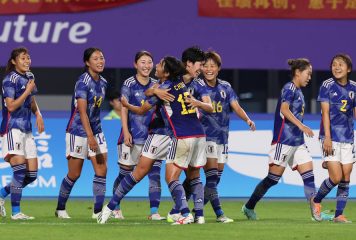隠れて流した涙から18年 両手を握りしめ「やっと叶った」…ベテラン主将が流した涙の重み

千葉CB鈴木大輔は昇格PO決勝で勝利し涙
J1昇格プレーオフ決勝・ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスの一戦。千葉のJ1昇格を告げるタイムアップのホイッスルが鳴り響いた瞬間、35歳のベテランCB鈴木大輔は目に涙を浮かべながら、その場に跪いて両手を握りしめて喜びをあらわにした。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
満面の笑みで喜ぶのではなく、「やっと叶った」という安堵と、これまでの想いを交錯させながら、自分の中でこの瞬間を噛み締めているように見えた。ヒーローインタビューでもあふれる涙を堪えきれず、何度も目頭を抑えた。
それだけ熱い想いと苦しんできた想いがあった。
鈴木が千葉にやってきたのは2021年のこと。年齢はすでに31歳に達し、キャリアの晩年に差し掛かるタイミングだった。星稜高から2008年にアルビレックス新潟に加入し、ロンドン五輪出場を経て、2013年から柏レイソルで3年間プレー。日本代表にも選ばれた。2016年から3年間、スペイン2部のジムナスティック・タラゴナでプレーし、帰国後は柏、浦和レッズを経て、千葉にやってきた。
紆余曲折を経てやってきた千葉で、サッカーキャリアで初となるJ2リーグを経験した。そして加入1年目からその人間性とキャプテンシーを認められてキャプテンに就任した。しかし、チームの先頭に立つも結果が出ない日々が続いた。2021、2022年は順位も思う様に上げられずに低迷し、2023年はプレーオフ準決勝で東京ヴェルディに敗れ、涙を飲んだ。
そして昨年は6月22日のJ2リーグ第21節の栃木SC戦のウォーミングアップ中に左アキレス腱断裂の大怪我を負い、シーズンを棒に振り、チームも7位に終わった。
J1が遠かった。他クラブではキャプテンは年によって変化をするが、鈴木はキャプテンとしてチームの先頭に立ち続けた。その苦悩の日々はかなり苦しかったはず。それでも真っ直ぐに前を見続け、チームのために率先して行動し、利他の精神と自分のパフォーマンスにこだわりを持ってストイックにやってきたからこそ、歓喜の瞬間は訪れ、前述したような姿をピッチの上で見せたのだろう。
思い起こせば、鈴木のキャプテンシーの凄まじさは星稜高校時代から相当なものがあった。
「僕は相当な負けず嫌いなのですが、そういう感情をあまり表には出したくないんです。自分の感情でチームに悪影響は与えたくないですし、あくまでチームとして勝利を掴むということに集中したいので。キャプテンをやっているのも、僕はまだまだ未熟者なので、一つ一つ壁にぶち当たりながら成長していきたいと思ってやっていますから」
高校3年生とは思えない、落ち着いて自分の客観視した言動だった。常に冷静さを保ちながらも、心にはとてつもなく熱い想いを持っている。
筆者が今でも忘れられないのは、高校3年生の時の佐賀インターハイでの姿だ。国見、流通経済大柏を倒して北信越勢初の決勝進出の立役者となりながらも、市立船橋との決勝戦は出場停止でスタンドから食い入るように見つめていた。失点を重ね、1-4になった試合終盤にはユニフォームに着替えて、表彰式に備えてベンチ裏の通路の下でただじっとピッチを見ていた。
そしてタイムアップのホイッスルが鳴ると、仲間たちに拍手を送り、1人1人と握手をして、表彰式ではキャプテンとして毅然とした立ち振る舞いを見せた。その後の取材対応を含め気丈に振る舞っていた鈴木が、ロッカールーム外のスタジアムの端で隠れながら涙を流す姿をたまたま目にした時は、キャプテンとしての責任感と根っからの負けず嫌いさを垣間見ることができた。
あれから18年。35歳になった今も変わらぬ、いや、より研ぎ澄まされたキャプテンシーを持って千葉をJ1昇格に導いた。
18年前の涙と今の涙の重みは変わらない。若い選手はまだまだ鈴木から学ぶことは多いし、伝えなければいけないことはたくさんあるはず。J1の舞台でキャプテンマークを巻いて力強く立つ鈴木の姿を早く見たい。
(安藤隆人 / Takahito Ando)
安藤隆人
あんどう・たかひと/岐阜県出身。大学卒業後、5年半の銀行員生活を経て、フリーサッカージャーナリストに。育成年代を大学1年から全国各地に足を伸ばして取材活動をスタートし、これまで本田圭佑、岡崎慎司、香川真司、南野拓実、中村敬斗など、往年の日本代表の中心メンバーを中学、高校時代から密着取材。著書は『走り続ける才能達 彼らと僕のサッカー人生』(実業之日本社)、早川史哉の半生を描いた『そして歩き出す サッカーと白血病と僕の日常』、カタールW杯のドキュメンタリー『ドーハの歓喜』(共に徳間書店)、など15作を数える。名城大学体育会蹴球部フットボールダイレクターも兼任。