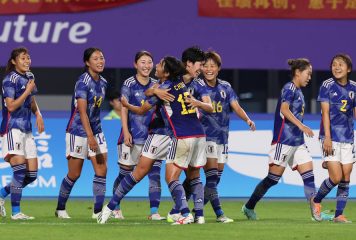浦和では味わえなかった経験「選手からすれば幸せ」 新天地で芽生えた“この人たちのために”

連載「青の魂、次代に繋ぐバトン」:田中達也(アルビレックス新潟U-18監督)第4回
日本サッカーは1990年代にJリーグ創設、ワールドカップ(W杯)初出場と歴史的な転換点を迎え、飛躍的な進化の道を歩んできた。その戦いのなかでは数多くの日の丸戦士が躍動。一時代を築いた彼らは今、各地で若き才能へ“青のバトン”を繋いでいる。指導者として、育成年代に携わる一員として、歴代の日本代表選手たちが次代へ託すそれぞれの想いとは――。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
FOOTBALL ZONEのインタビュー連載「青の魂、次代に繋ぐバトン」。ミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任後、田中達也は浦和レッズでの出場機会を減らし、アルビレックス新潟に移籍した。それまでと異なる環境でチャレンジし、プレースタイルも変化。若手時代から変わらない情熱で、9シーズンにわたってチームを支えることになる。(取材・文=二宮寿朗/全5回の4回目)
◇ ◇ ◇
自分にとって良い監督とは?
極論を言えば信頼して使ってもらうとその範疇に入る一方で、自分を使わない人に対してはどこか反発したくなるのがフットボーラーの一般的な心情ではないだろうか。
田中達也は、浦和レッズ12年目となった2012年シーズン、キャリア最低のリーグ戦7試合の出場にとどまった。新指揮官に就任したミシャことミハイロ・ペトロヴィッチのもとでは、ピッチに立つことが難しくなっていた。
「ミシャさんの(チームの)1トップをやるには自分の基本技術が足りなさすぎました。相手を背負いながらしっかりコントロールするとか、ワンタッチで正確に落とすとか、求められたものをやれなかったので(試合に出られないのは)納得していました。
ミシャさんは本当にすごい。普段トレーニングでやっているプレーがそのまま試合に出るんです。それってプロの現場ではなかなか難しいのに再現性が高いし、見ていて楽しいサッカー。だからミシャさんみたいな監督になりたいって、本人に会ったときにはよく言っていましたよ」
ミシャのサッカーに順応しきれていないことは誰よりも自分自身が理解していた。ちょうど30歳になるシーズン。覚悟はしていたとはいえ10月末に契約満了を通達されると、思った以上にへこんでしまう自分がいた。
チーム最年長の山田暢久にだけ事実を伝えたのは、ACL出場権を懸けたシーズン終盤の戦いに集中してほしかったから。いつもと変わらず、練習に精いっぱい打ち込む姿があった。ようやくチームメイトが知ることになったのは、11月終わりごろだったという。
2012年12月2日、名古屋グランパスとの最終節。2-0と勝利して3位を確定させACL出場権を手にしたことでにぎわう埼玉スタジアムにおいて試合後、田中の退団セレモニーが行われた。2003年のヤマザキナビスコカップ決勝でゴールを奪い、両手を広げて喜ぶ彼のゴールセレブレーションを模した赤と白の絵が、サポーター席に浮かび上がった。田中は目に焼きつけるかのように、まばたきもせず見つめていた。
サポーターへの挨拶では言葉に詰まり、何度も涙を拭った。そして感謝の言葉を繰り返した。
田中が当時を思い起こす。
「レッズの最後のほうは、ケガが続いてチームの力になれなくて。そんななかでも自分を応援してくれる声援だったり、ファンレターだったり……。みんなの言葉に励まされて、支えられましたから。もう本当に感謝しかなかったですね。次にサッカーをやるところで元気な姿を見せることで恩返しになればと思いました」
そう、田中達也のストーリーは終わらない。
体が悲鳴を上げるまで鍛えた、新潟での刺激的な日々
レッドからオレンジへ。新天地となるアルビレックス新潟にはちょっとした運命めいたものを感じていた。右足関節脱臼骨折の大ケガから2006年に復帰した試合の相手がアルビレックスであり、会場もビッグスワンだったからだ。リスタートしていく自分を自然と重ねていくことができた。
チームを率いる柳下正明からはインテンシティとハードワークを求められた。そこにベテランも若手も関係ない。新しい環境での横一線の競争は、とても刺激的であった。
「トレーニングの強度が本当に高くて、30歳を過ぎてから若い選手と同じようにもう1回、体が悲鳴を上げるまで鍛えられたことが大きかった。あれだけトレーニングをして(試合に)臨むので、自信を持ってピッチに立てたというところもあります」
なるべく体を休ませず、無理を強いた。強い体づくりに取り組むことで、ケガがちな肉体を克服したいという思いもあった、
開幕からスタメンを張り、5月18日ホームでの大分トリニータ戦で待望の初ゴールをマークする。そして迎えた8月31日、埼玉スタジアムに乗り込んでの古巣レッズ戦。スタメンの発表でコールされると浦和のスタンドからはブーイングではなく、温かい拍手が注がれた。
移籍1年目は34試合中32試合に出場して2得点。大きなケガなく1年間を戦い抜き、チームは3年ぶりに1ケタ順位の7位でフィニッシュする。田中自身ドリブルで勝負しつつもそこばかりに固執せず、プレースタイルにも変化をつけていた。
「30歳を超えて、若いときのようなドリブルはできない。自分なりに考えたのは選手として生き延びていくにはどうすればいいか。ハードワークしたり、ライン間でボールをうまく受けたり、できることを正確に、最大限にやろうとしました。逆にできないことはできないので、そこは隠しながらプレーしようとしていましたね」
あと2、3シーズンでのキャリアの終焉を想像した人も多くいたに違いない。だがアルビレックスでは9シーズンにわたってプレーし、39歳まで現役を続けることができた。
メンバーが入れ替わっても支えてくれるサポーターに感謝
レッズでは味わえない経験もあった。国内のビッグクラブであるレッズは有能なタレントを集めてくるが、逆に経営規模が大きくないアルビレックスは主力選手が引き抜かれていく現実があった。柳下が退任以降は指揮官も目まぐるしく交代し、J2降格も経験した。それでも応援してくれるサポーターたちがいた。レッズ時代と同じように、支えてくれるこの人たちのために戦いたいと思えた。
「本当に毎年、メンバーがメチャメチャ入れ替わるんですよね。12、13人くらい入れ替わったシーズンもあったんじゃないかな。(18年からは)J2で戦うようになっても、それでもデンカビッグスワンスタジアムに集まって、応援してくれる。選手の立場からすれば幸せでしかなかったですね」
30代半ばに入ってからは控えに回ることが多く、出番がないことも珍しくなくなった。それでもトレーニングから全力を尽くし、試合のメンバーに選ばれなかったら悔しい気持ちがこみ上げる。若いころとまったく変わらない日常があった。
「試合に出られないからふて腐れるとか、どうして自分を使わないんだっていう感情を表に出すとか、そういうことをしても何もプラスにならないことは昔からずっとあったので。若いころに見ていたベテランの人は、常に自分に矢印を向けていました。トレーニングはいつも100%で、チームのために鼓舞して。だから自分もそれを実践しただけに過ぎません。試合前日は軽いトレーニングメニューになりますよね。ベンチに入らないのに、この量だと足りないので(同じベンチ外の選手たちと)じゃあシュート練習やろうか、とかそういうことも周りのメンバーと一緒にやっていました」
2021年シーズンも、ホームゲームでのラスト1試合となった。田中達也に、ついに決断のときが訪れた。(文中敬称略/第5回に続く)
■田中達也 / Tatsuya Tanaka
1982年11月27日生まれ、山口県出身。帝京高校から2001年に浦和レッズに加入し、1年目からプロ初ゴールを挙げるなど、J1リーグ戦19試合に出場。03年にはナビスコカップ(現・ルヴァンカップ)で大会MVPとニューヒーロー賞を獲得する活躍で優勝に貢献し、浦和に初タイトルをもたらした。13年にアルビレックス新潟に移籍し、21年の現役引退まで9年間在籍した。引退後は新潟トップチームのアシスタントコーチを務め、25年からは新潟U-18の監督を務めている。
(二宮寿朗 / Toshio Ninomiya)
二宮寿朗
にのみや・としお/1972年生まれ、愛媛県出身。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。2006年に退社後、「Number」編集部を経て独立した。サッカーをはじめ格闘技やボクシング、ラグビーなどを追い、インタビューでは取材対象者と信頼関係を築きながら内面に鋭く迫る。著書に『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『岡田武史というリーダー』(ベスト新書)、『中村俊輔 サッカー覚書』(文藝春秋、共著)などがある。