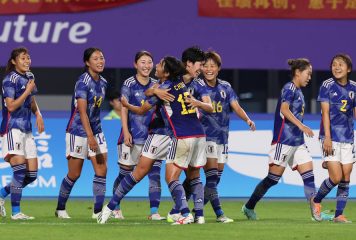今季のJにあった「7月の境界線」 1.3枚→2.9枚に倍増…審判から見る“世界基準”

今季Jリーグは「アドバンテージ」を積極的に適用した
2025年が終わろうとしている。今シーズンのJリーグを振り返ると、ピッチ上の攻防だけでなく、「レフェリング」においても大きな変化が見られた1年だった。J1リーグのデータを紐解くと、日本サッカーの進化と、世界との間に横たわる「埋めなければいけない課題」が浮き彫りになってくる。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
今季のレフェリングにおいて特筆すべき成果は、「アドバンテージ」の積極的な適用だ。クリティカルなファウルでない限り、プレーが続いていれば笛を吹かずに流す。これはシーズン前に日本代表の森保一監督からも要望があった点だが、実際の運用は当初簡単ではなかった。
シーズン当初には、いくつかのクラブから「怪我につながるのではないか」と懸念の声が上がった。しかし、ヨーロッパから帰国した選手たちがその強度と基準を周囲に伝播させたことも奏功し、次第に選手側も順応した。プレーを止めずにチャンスを作り出す姿勢が定着していった。
この意識変化は、警告のデータにもはっきりと表れている。2024年と比較して、「反スポーツ的行為」の警告は17%減、「ラフプレー」も10%減少した。プレーが止まらないため、これまでならイエローカードが出ていたプレーが「注意」で済むケースが増えたからだ。安易にファウルで止められない環境が、選手たちのプレーレベルを一段階引き上げたと言えるだろう。
一方で、激増した数字がある。「異議」に対するイエローカードだ。その数は昨季の2倍近くに達している。
興味深いのはその推移だ。開幕から7月(E-1選手権)までの第23節までは1節あたり約1.3枚だったが、第24節以降は2.9枚と倍以上に増えている。この「7月の境界線」には明確な理由がある。
それは日本サッカー協会が実施したレフェリー交流プログラム。5月から6月にかけ、ドイツ、イングランド、ポーランドから審判員を、そしてブンデスリーガの審判インストラクターであるペーター・ジッペル氏を招聘している。ペーター氏は日本の課題として「選手やテクニカルエリアのマネジメント」を指摘した。
実際、来日した欧州のレフェリーたちは、勢いよく詰め寄る選手に対して躊躇なくカードを提示した。日本のレフェリーたちはその「世界基準」を目の当たりにし、後半戦から基準を厳格化したのだ。本来、異議は「キャプテンオンリー」のルールもあり、減るべきものだが、この過渡期において数字が増えたのは、日本が正しい方向へ舵を切った証拠とも言える。
しかし、まだ踏み込みきれていない聖域がある。「ベンチマナー」への対応だ。
ACLなどの国際舞台では、判定に対してベンチから飛び出す行為は即座に警告の対象となり得る。ピッチ内の選手同様、ベンチワークにも厳格な規律が求められるのが世界の常識だと言えるだろう。
対してJリーグでは、ここに対してまだレフェリーが及び腰に見える。「バンバン警告を出せば試合が荒れる」という配慮が働くのかもしれない 。実際、2022年カタールワールドカップの1試合平均イエローカードが3.5枚だったのに対し、2025年Jリーグは2.5枚に留まっている。カードを出さずにコントロールしようとする苦労は窺えるが、その「優しさ」が仇となってはいないか。
ベンチマナーに目をつむらず、毅然と警告を出す。一時的に試合が止まるとしても、それが徹底されれば、チームの意識は「審判への文句」よりも「次のプレー」に向くようになるはずだ。
2026年シーズン、Jリーグが真に世界基準のタフなリーグへ脱皮するためには、ピッチ上のアドバンテージだけでなく、ベンチを含めたマネジメントの厳格化が不可欠だ。審判は脇役だが、日本サッカーをワールドカップ仕様に引き上げる重要な演出家でもある。来季は選手のプレーだけでなく、レフェリーの毅然とした「強さ」にも期待したい。
(森雅史 / Masafumi Mori)

森 雅史
もり・まさふみ/佐賀県出身。週刊専門誌を皮切りにサッカーを専門分野として数多くの雑誌・書籍に携わる。ロングスパンの丁寧な取材とインタビューを得意とし、取材対象も選手やチームスタッフにとどまらず幅広くカバー。2009年に本格的に独立し、11年には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌で開催された日本代表戦を取材した。「日本蹴球合同会社」の代表を務め、「みんなのごはん」「J論プレミアム」などで連載中。