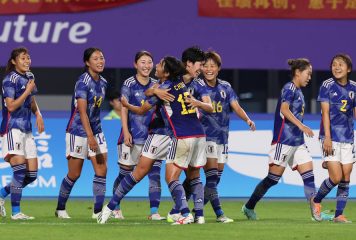代表から帰還も3軍扱い「どうするんだ」 試合後に“ヤケクソ”…差し伸べられた「使っちゃうよ」

石川直宏氏のデビュー戦はボランチでの出場だった
現役時代、FC東京で長年にわたり活躍した元日本代表MF石川直宏氏。2000年に横浜F・マリノスのトップに昇格したものの、チャンスを掴めない日々。ワールドユースで10番をつけた男に意外な場所で転機が訪れた。(取材・文=FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎/全7回の3回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
大逆転でつかんだマリノスでのトップ昇格。だが膝の半月板損傷の怪我を負いながらも痛み止めを飲んでプレーし続けた代償は大きく、秋に仮契約を締結後に手術を実施。3か月のリハビリからプロ生活がスタートした。
「キャンプインに間に合わせようということで、高校も卒業していないユース出身の僕が、トップチームのトレーナーにリハビリしてもらえました。でも僕が行けるのは高校が終わって夕方ぐらい。そのトレーナーは、トップの選手たちが帰った後に、僕がどれだけの実力があるのかも知らないのに、夜まで付き合ってくれたんですよ。3か月間ずっと。トレーナーからは『君さ、トップで活躍できる選手なの?』って言われていて。そうだなと思いながら、『活躍できるかどうか分かんないですけど、頑張って活躍します』って返していました」
開幕前のキャンプから合流。3か月かけてリハビリをこなしたからこそ、膝への違和感はなかった。意外にも早くデビューの時は訪れた。4月1日に行われた国立競技場での第4節・鹿島アントラーズ戦。後半43分から初めてプロのピッチに立った。
「当時のアルディレス監督は結構若手を使う監督だったんです。でも最初に出たポジションはサイドじゃなくて、ボランチでした」
もちろん、ボランチはそれまでやったことはなかった。指示は鹿島の中心選手であるビスマルクに「ボールを触らせるな」。ただただ無我夢中で食らいついた。おまけに勝ち越しゴールの起点となり、3-2での逆転勝ちを呼び込んだ。
「ビスマルクにずっとついていって、ボールに触らせない、ボールを持たれたら当たりにいくことが役割でした。準備をしっかりすることも、監督のニーズに合わせてプレーすることもそうですし、そういうこともあるんだなってことを学べました。アディショナルタイムを含めて数分間、ワンタッチかツータッチぐらいしたかな。でもそれが起点になってゴールにつながったんです。試合に勝ったのは今でも覚えています」
幸先良くデビューしたものの、当時のマリノスは中村俊輔を筆頭に、三浦淳宏、松田直樹、川口能活、柳想鐵と代表レベルの選手がずらりと並ぶ豪華なラインナップだった。1stステージで優勝を果たすなど成熟したチームの中で、快足自慢のルーキーは、生き残るすべを見いだせないでいた。
「この世界の中でどう生きていったらいいのか分からなかったですね。スピードもパワーも判断も経験も違う。アルディレスは独特で、ウォーミングアップでは、センターサークルにみんな並んで、真ん中に4人が入るんです。うち3人は鬼役で、1人はターゲット。ミスしたら、ミスした選手と両隣の選手が真ん中に入るんですよ。だからミスしてなくても隣にいたら入らなきゃいけない。ここで自分がダフったりしたらと思うと、やっぱりダフる。そしたら先輩たちが横から僕の顔をにらんで、『お前行けや!』って(笑)。本当に怖かったし、練習に行きたくなかったですもん(笑)」
支えとなっていたワールドユース
1年目の2000年、リーグ戦の出場は2試合でたった3分間に終わった。一方で、翌年のワールドユースを目指す世代別代表の活動には中心選手として継続して参加。後に名を成す多士済々のライバルたちにもまれ、モチベーションを維持していた。
「もうそれが助かったんですよね。ナビスコ杯とか天皇杯は出ていたんですけど、リーグ戦になかなかつながっていかない。でも世代別代表の活動があの時は月1ぐらいであったので。試合に出ている選手が優先的に選ばれていましたけど、僕も早めにJリーグデビューしていたので、注目していただくようになって、呼んでもらえていたんです。ライバル視してる選手はいっぱいいましたけど、京都で出ていた松井大輔とか、あとはポジション違いますけど、森崎和幸とか阿部勇樹、山瀬功治とか。常連は駒野友一や、一個下だと青木剛とか佐藤寿人、前田遼一とか。日の丸を背負うのは初めての経験でしたし、ワールドユースが翌年にアルゼンチンであるということで、モチベーションを持っていけてましたね」
一つ上の世代は、小野伸二、高原直泰、稲本潤一、遠藤保仁らがいた「黄金世代」。ナイジェリアでワールドユース準優勝を果たした彼らの強烈な光に圧倒され、石川たちは「狭間の世代」「谷間の世代」と呼ばれた。だがその反骨心が、後の成長につながっていく。
「僕らの世代はもう反骨心。ただ逆に言えば、親近感もあった。ファン・サポーターもそうですし。キャラクターも含めてなんか応援したくなるというか。世界レベルの大会で結果は出てないですし、そう言われてもしょうがないっていうのはありましたけど、これをどう覆すか、みたいな。監督の西村昭宏さんも、後にアテネ五輪代表監督になる(山本)昌邦さんも言ってました。いい意味での共通キーワードになってましたね」
10番を背負って臨んだワールドユースは、1勝2敗でグループステージ敗退に終わった。その間、マリノスは監督が交代。怪我もあり、立場は追い込まれていった。
「ワールドユースに行ってる時に監督がラザロニというブラジル人に変わって、帰ってきたらもう自分の居場所がなかった。2ndステージで1回だけ出ましたけど、その後は腰のヘルニアで4か月プレーができなくて、3年目はいわゆる“ハブ練”で、3軍みたいな扱いをされて。怪我も治って自分の中ではしっくりくるパフォーマンスなんだけど、監督が見る機会も全然ないし、評価されない。世代別代表ではアテネ五輪に向けた合宿も始まっていて、ほとんどの選手がクラブで試合に絡んでいる。どうするんだってなっていました」
くすぶっていた石川に声を掛けたのは、当時FC東京の監督を務めていた原博実だった。ワールドユースの解説もしていた元日本代表ストライカーの指揮官は、石川のアタッカーとしての能力と反骨心を高く評価し、自らのクラブに期限付きで招き入れた。だが最後の決め手となったのは意外な理由だったという。
「今でも覚えてますけど、2002年シーズンが始まってすぐの4月に、FC東京とのサテライトリーグがあったんです。でも僕は後半の残り15分ぐらいしか出られなくて。腹が立ちすぎてイライラしていて、試合後にみんなはロッカーに帰っているのに、『なんでこんなにうまくいかねえんだ』って、ずっとボールをかき集めてゴールにバッコンバッコン蹴っていたんです。そんな姿を遠くから原さんや当時のFC東京の鈴木徳彦さんや長澤徹さんたちが見ていて、『あいつを呼ぼう』ってなったと聞きました。
原さんは自分の存在やマリノスで出られていない境遇も知っていたんです。試合後にボールを蹴っていたエネルギーをうちで使ってくれっていうような。で、原さんの口説き文句『今来たら使っちゃうよ』っていう(笑)。自分も藁をもつかむ思いじゃないですけど、でもやっぱりFC東京で『これだけできるんだぞ』って見せて、ある意味マリノスをギャフンと言わせて、帰ろうということしか考えてなかったです」
この出会いが、石川を、そしてFC東京の運命を大きく変えていくことになる。(第4回に続く)
(FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue)