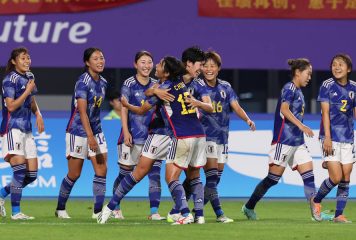10歳でプロ諦め…大学で転機「やってみないか?」 中国人審判が影響を受けた日本の名主審「完全に無視」

中国人審判員のフー・ミン氏に話を聞いた
日本サッカー協会審判部が行っている「交流プログラム」では、海外サッカー協会と審判員が相互に派遣される。今年はこのプログラムに加え、数多くの国際大会で笛を吹いてきたアジアトップクラスの審判員であるフー・ミン氏が来日している。フー・ミン氏とはどんな人物なのか、そして影響を受けた日本の審判員は誰か、聞いた。(取材・文=森 雅史/全2回の1回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
——そもそもなぜサッカーの道に進もうと思ったのですか?
私は中国で普通の家庭に生まれ、父の影響でスポーツ、特にサッカーを深く愛するようになりました。父は若いころプロ選手で、私の最初のコーチでもありました。よく私をグラウンドに連れて行っては、サッカーを職業にするよう励ましてくれました。
10歳の時、父と真面目に話し合いました。父は「プロサッカー選手になりたいなら、家を離れて別の地域でトレーニングと勉強をしなければならない。それでいいか?」と私の意志を確認してきました。私は「いや、離れたくない。ここにいて、勉強を続け、友達と一緒にいたい。どうして離れなければいけないの」と答え、家にいるほうを選択しました。
実際のところ、プロ選手になるのはとても難しいことです。才能に加えて努力が必要ですが、それでも早期引退の可能性もあります。だから私は学校でサッカーを続けることにしました。そして高校まで、常に学校のチームで試合に出場したのです。
——大学に進学したあとはどんな選択があったのですか?
大学ではスポーツ専門大学でサッカーを専攻し、大学リーグでプレーしました。その間、ピッチ上で様々なポジションを経験しました。ボランチ、右ウイング、そして最終的にはCBです。最終学年では、キャプテンに任命されました。
大学時代の指導教官の1人はとても優れた審判員でした。2年生のとき、彼が「審判をやってみないか?」と声をかけてくれたんです。これが私の審判人生の始まりです。彼に指導してもらいながら、現役選手としてプレーしつつ審判活動を始めると、競技規則を学ぶほど自身のプレーが向上することに気づきました。
そして3年生からはプロ審判の養成課程と資格取得を開始し、アマチュア試合から上位大会へと段階的に昇格していったんです。試合開始からタイムアップまで軽々と走り続けられる高い身体能力があったおかげで、審判に要求されることに十分対応できました。
これが私が優秀な審判に成長できた決定的な要因だと確信しています。フィットネスは基本であり、常に私の基盤なのです。
——ですが審判として辛かったことも経験しているでしょう。
審判にとって最大の試練は試合中にミスが発生したときです。内外からのプレッシャーは圧倒的になります。そういうことが起きたとき、心構えを調整し、試合後にプロフェッショナルな分析を行う方法を学ぶことは、すべての審判が習得すべき課題です。
もちろん人間である以上、誰もがミスをします。あらゆる努力を払っても、過ちは起こるのです。自分がミスをしたときは、深い悔しさを感じます。しかし、サッカーは予測不能で、どんなに準備を整えても、予期せぬ状況は発生しうるのです。
偶然ですが、私は大学で「審判員の心理メカニズムと調節システム」に焦点を当てて研究しています。審判員がプレッシャーをより効果的に管理するための心理的「サポートシステム」を開発することが目標なのです。
——多くの批判に対してどう対処するのがいいのですか?
試合中は、自分自身を完全に信頼し、決して判断を疑ってはいけません。試合後に誤りに気づいた場合は、分析し、メモを取り、解決策を特定して、将来同じ過ちを繰り返さないようにします。
私には、SNSでの批判やコメントをコントロールすることができません。だから完全に無視することにしています。私はSNSアカウントを一切持ちません。これは西村雄一氏(JFA審判マネジャー)がかつて私に教えてくれたことです。
「議論は他人に任せよう。それは彼らの問題だ」と思っています。審判の義務は単純明快なのです。ミスを分析し、解決策を見つけ、向上し続けること。それ以上でも以下でもありません。(第2回に続く)

森 雅史
もり・まさふみ/佐賀県出身。週刊専門誌を皮切りにサッカーを専門分野として数多くの雑誌・書籍に携わる。ロングスパンの丁寧な取材とインタビューを得意とし、取材対象も選手やチームスタッフにとどまらず幅広くカバー。2009年に本格的に独立し、11年には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌で開催された日本代表戦を取材した。「日本蹴球合同会社」の代表を務め、「みんなのごはん」「J論プレミアム」などで連載中。