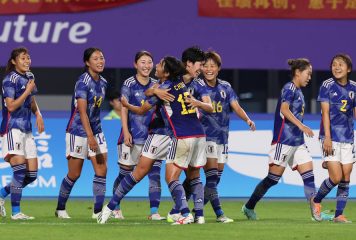“週末だけプレミアリーグ”からの脱却 文化定着の秘訣は「フットボールしすぎない」

日本にプレミアリーグを文化として根付かせる“使命感”
イングランド・プレミアリーグは現地時間8月15日(日本時間8月16日)、2025-26シーズンの開幕を迎える。三笘薫(ブライトン)や遠藤航(リヴァプール)など多くの日本人選手が活躍する世界有数のリーグは日本でも高い関心を集めている。FOOTBALL ZONEでは、昨季からプレミアリーグを国内で独占配信する「U-NEXT」のTV・スポーツ本部フットボール部長の榎本耕次さん、同担当部長の菅原慎吾さんにインタビューを実施。日本でプレミアリーグの文化をさらに広げていくためにはどのような取り組みが必要なのかを語ってもらった。(取材・文=石川遼/全3回の3回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
「U-NEXT」は、2024-25シーズンから7年間の長期契約でプレミアリーグの独占放映権を獲得した。昨季はリバプールが5季ぶりの優勝を果たして大いに盛り上がりを見せたが、試合を配信する立場から今後はその人気をさらに拡大させて、日本にプレミアリーグを文化として根付かせていくことが“使命”となる。
スペインのラ・リーガに精通する菅原さんは、プレミアリーグの人気の秘訣について「1年間やってみて感じたのは好守の切り替えが多くて本当に面白いということ。そして、各クラブにしっかりとしたファンベースがあることで、毎回コンスタントに見てもらえている」と分析している。そのうえで「2年目以降は各クラブのファンを増やすような動きに力を入れていきたい」と今後の戦略を明かした。
ただし、そこで気をつけなければならないのは、サッカー色を強くしすぎないことだという。例えば、その週の試合結果を集めたハイライト番組はサッカーファンからの需要は高いが、そこから新たな広がりにはつながりにくい。榎本さんも、菅原さんと同様にファンベースやファンコミュニティーの強化は重要だとしつつも、新規やライト層に向けては「新しいベクトルでのアプローチが必要」だと語っている。

新規ファン獲得の鍵はジャンルの垣根を越えたクロスオーバー
そんな「新しいベクトル」の一つの例が、「フットボール×食」「フットボール×音楽」「フットボール×街」といった他のジャンルとの“かけ合わせ”による楽しみ方の提供だ。幅広いジャンルの中から、ファンがそれぞれに好きな組み合わせを見つけられれば、その可能性は無限大に広がる。
榎本さんは女性アイドルが「フットボールが好き」と言ってニュースになることを例に挙げる。「『フットボール』ではなく『女性アイドル』カテゴリーのニュースとして発信されれば、ジャンルの垣根を越えてクロスオーバーし、新規ファンの獲得にもつながります。フットボールファンの中に閉じてしまうのではなく、こうしたクロスオーバーを組み合わせることで、他のファン層にもリーチできるはずです」と説明する。
「そういう意味では我々は相性がいいはずです。アイドルの音楽ライブも見られますし、雑誌や写真集も見ることができます。このストロングポイントを生かすことが、フットボール文化を広げていくためにも重要になってくると考えています」

プラットフォームとして見据える“試合がある週末だけの話題“からの脱却
誰でもスマートフォン1つで手軽に娯楽に触れられる今の時代、ユーザーの可処分時間を奪い合うのは野球やバスケットボールなど他のスポーツだけではなく、音楽や映画、ゲームなどあらゆるジャンルのコンテンツだ。だからこそ、異なるジャンル同士をかけ合わせて楽しむことができる環境づくりがマストになる。
「フットボールと他のジャンルとの掛け合わせによって接地面をできるだけ大きくしていくこと。来季は、日々の生活の中でコンスタントに触れ続けられるものになってもらうように取り組んでいます(榎本さん)」。うまくいけば一つひとつの足し算ではなく、2倍、3倍と膨れ上がる相乗効果が期待できるはずだ。
これまでプレミアリーグを見てこなかった人たちにも見てもらえるように――。榎本さんはそれこそが独占放映権を持つプラットフォームとしての大きな目標だと話す。そして、そこにたどり着くためには、“試合がある週末だけ話題になる”という習慣を変えることが大きな課題になるという。
今後は日本未上陸の現地番組やコンテンツの調達を検討中。「深掘りできる土壌を耕しながらも、視野を広く持つこと“フットボールフットボールしすぎない”ということは、僕らが考えている一つの大きなテーマ。来季は試合のない平日にも楽しめるコンテンツが増えていくので、期待してください」。サッカーという枠組みを越えていく大いなる挑戦はまだ始まったばかり。彼らが見据えるサッカー界の未来に期待したい。
(石川 遼 / Ryo Ishikawa)