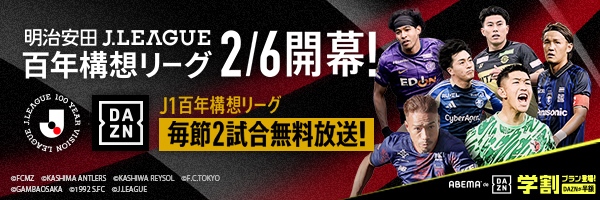海外審判団から言われた「そんな対応で良いのか」 日本人との”差”を指摘「学ぶべきところ」

レフェリーブリーフィングを実施
日本サッカー協会(JFA)は7月2日にレフェリーブリーフィングを実施した。海外から審判を招いて行う審判交流プログラムの報告では、欧州3か国の審判団とインストラクターから選手やチーム役員の抗議への対応が「優しい」という指摘があったと話された。
【PR】ABEMA de DAZN、2/6開幕『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』全試合生配信!毎節厳選6試合は無料!
各国から審判を招き、主にJリーグやWEリーグの試合を担当してもらう交流プログラムについて、今回はドイツ、イングランド、ポーランドの3か国から招いた審判団との意見交換について報告された。JFA審判委員会の佐藤隆治マネジャーは「最も大きかった学びは、競技規則をベースにして彼らはガイドラインを持っている。レフェリーだけでなくリーグやクラブに伝えながらやっている」という要素を挙げた。
なかでも、インストラクターのペーター・シッペル氏も含む欧州の審判員たちから指摘されたのは「判定はおかしいと思わないし求めているものは変わらないが、対選手だけでなくチーム役員へのマネージメントは優しいと言われた。場合によってはレフェリーの判定が間違っていることもあるが、そうであっても選手やテクニカルエリアの役員が攻撃的なアクションを取ることには厳しく対応するガイドラインでやっているとのことだった」と、佐藤マネジャーは話した。
具体例として、京都サンガF.C.とセレッソ大阪の試合の前半37分過ぎに京都の選手のファウルを取りイエローカードを提示したが、そこに抗議を行ったC大阪の選手に対し即座にイエローカードを提示した場面、サンフレッチェ広島と川崎フロンターレの試合の後半アディショナルタイムに広島のFW前田直輝を警告した場面、川崎フロンターレとヴィッセル神戸の試合で後半開始直後に神戸のDF酒井高徳にイエローカードを出した場面が挙げられた。
いずれも今回の交流プログラムで来日していた審判員たちが主審を担当したゲームだった。佐藤マネジャーは酒井のシーンを例に挙げ「最初の接触をどう判断するかは議論があるかもしれないが、選手のアクションが認められるかは別の話」とした。そして、「日本のレフェリーたちは、そんなに優しい対応で良いのかというのは言われた」と、今回の交流プログラムで受けた意見について話した。
また、佐藤マネジャーは「すぐに、抗議に対してイエローカードを出す。厳しいのではないかという感想を持つかもしれない。ただ、明らかにアグレッシブなアクションをしている。躊躇なく毅然とカードを出すところは、学ぶべきところ、合わせていかなくてはいけない基準と感じた」とも話した。
扇谷健司審判委員長は「欧州3か国のレフェリーが同じ対応をしているところにスタンダードが整理されていると感じる。このようなスタンダードを合わせていくの大事だと思う。クラブW杯でも異議のカードは厳しく出ている」と話す。抗議に対して審判が柔軟に対応し過ぎることは、プレー以外で浪費される時間が増え、アクチュアル・プレーイングタイム(実質的なプレー時間)の現象にもつながる。そのような意味でも、審判交流プログラムから得た学びになったと言えそうだ。
(FOOTBALL ZONE編集部)