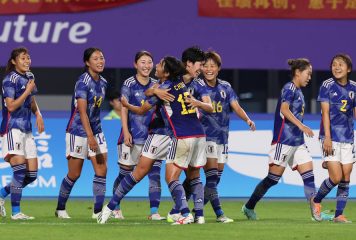“黄金世代”がつなぐバトン 食事をコーラでごまかした過酷環境‥トルシエから言われた「日本人は弱い」を覆すヒント

“黄金世代”の石川竜也氏が当時を回顧「ブルキナファソで忍耐力を養った」
2026年北中米ワールドカップ(W杯)で世界一を目指している日本代表。しかしながら、これまで7大会の最高成績はベスト16。決勝トーナメントを勝ち上がって決勝まで辿り着き、そこで重圧のかかる大一番を戦うというのは、日本男子サッカー界にとってあまりにも高いハードルなのだ。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
その領域を経験したチームが過去に1つだけある。99年にナイジェリアでのU-20ワールドユース(現U-20W杯)で準優勝したU-20日本代表である。
小野伸二(Jリーグ特任理事)ら1979年生まれの“黄金世代”がフィリップ・トルシエ監督の下、ポルトガル、メキシコ、ウルグアイを撃破し、スペインとファイナルを戦った26年前の出来事は、今も多くの人々の脳裏に焼き付いて離れないだろう。
この大会に筑波大学の学生として唯一、参戦していたのが、左サイドバック(SB)・ウイングバック(WB)を担った石川竜也氏。現在はJ2藤枝MYFCのアカデミー・サブダイレクター兼U-15監督を務めている人物である。
左利きのテクニシャンだった彼の存在が広く知られたのは、グループリーグ第3戦・イングランド戦。精度の高い間接FK弾を叩き込み、名手として名を馳せたのだ。もう1つ印象的だったのが、準決勝・ウルグアイ戦。勝利した瞬間。トルシエに強引にキスされ、複雑な表情を浮かべる石川の映像がテレビ画面に大写しにされ、話題をさらったのだ。
「(トルシエの)ヒゲが濃くてジョリジョリするので、『わ、ヒゲ』ってなっちゃいました」と当時の彼は笑っていたが、今はトルシエと同じ指導者の道に進み、しかも当時の指揮官よりも年上の45歳になっている。
その石川に改めて26年前を振り返ってもらうとともに、なぜ黄金世代は突出した個性が育ったのか、どうしたら突き抜けたタレントを育てられるか……といった問いに対する意見や考察を存分に語ってもらった。(取材・文=元川悦子/全4回の1回目)
◇ ◇ ◇
「僕らはナイジェリア開催だったU-20W杯直前の99年2月にブルキナファソ遠征に行きました。バスでガタガタした道を何時間も走って試合会場へ行き、地元チームと試合をしました。泊まったホテルのベッドは埃をかぶっていて、食べ物も衛生的に難しいものが多かった。食べられるものが少なく、コーラとかでごまかす感じで体重も落ちました(苦笑)。
当時のトルシエはそういう僕らの姿を見て『日本人は弱い』と言っていました。やり方の善し悪しはともかく、あれは僕らにとってすごくいい経験だったし、逞しくなったのは間違いない。本大会でナイジェリアに行ってからは環境のことは何とも思わなかったし、自分たち本来の力を出せた。ブルキナファソで忍耐力を養った成果だったと思います。
今はコンプライアンス意識が高く、あのようなアプローチ方法は難しい部分もあるかもしれませんが、過酷な環境に放り投げられると人間は強くなるのは確か。今の子供たちもタフにさせるアプローチを考えていかないといけない。それは指導者になってから考えている大きなテーマです」
指導者として試行錯誤…旧友愛息との再会も「いろいろな経験を」
鹿島アントラーズ、東京ヴェルディ、モンテディオ山形での選手キャリアを終えて、2018年から指導者に転身した石川はしみじみとこう語る。確かに彼らが育った昭和・平成初期の頃と、令和の今は育成年代の環境が大きく異なっている。
2024年春には「不適切にもほどがある」というドラマが一世を風靡したが、サッカー界、スポーツ界で許されなくなったことは数えきれないほどある。「お前何やっているんだ」「下手くそ」といった言葉なども、パワハラとして捉えかねられない今、指導者が選手を鍛えていくのは本当に難しい。石川も日々、伝え方など試行錯誤している様子だ。
育成年代を長く指導したベガルタ仙台の森山佳郎監督が、久保建英(レアル・ソシエダ)や中村敬斗(スタッド・ランス)らがU-15~U-17日本代表だった頃、あえてインドやインドネシアといった環境的に難しい国に遠征し、ドロドロのグランドでプレーさせたというが、そういった工夫はやはり必要だと石川も言う。
「森山さんがトライしたことはすごく参考になると思います。僕は引退後、山形で指導させてもらって、トップ、ジュニア、ジュニアユースを見る機会に恵まれたんですが、『子供たちにはいろいろな経験をさせたい』と考えていました。そこで積極的に県外へ出ていくようにしました。東北エリアはもちろんのこと、北関東あたりまでは4時間くらいで行けるので、古巣・鹿島のアカデミーチームとも試合をさせてもらいました。
当時の鹿島ジュニアには満男(小笠原=アカデミー・テクニカル・アドバイザー)とソガ(曽ヶ端準=現鹿島GKコーチ)の息子(小笠原央と曽ヶ端輝)もいて、山形のフェスティバルに来た時にプレーしているところを見ました。なんだか感慨深いものがありましたね(笑)。彼らを見て、本当に技術レベルが上がっていると痛感したのと同時に、指導している選手たちをもっとタフにさせないといけない。そういう気持ちになったのも確かです」
石川の思いは黄金世代に共通するものかもしれない。2024年末の稲本潤一(川崎育成部コーチ)の現役引退によって“79年組”は全員がプレーヤーを離れたが、今はそれぞれがサッカーに関わり、日本のレベルアップ、次世代の育成に尽力している。
“黄金世代”は今も第一線をー次世代につなげるバトン
石川同様、指導現場に立っているのは、遠藤保仁(ガンバ大阪トップコーチ)、小笠原、手島和希(C大阪サッカースクールコーチ)ら。GKの南雄太も流通経済大学付属柏高校などでGKを指導しており、曽ヶ端も鹿島のトップチームで活躍している。
現場ではないが、中田浩二は鹿島のフットボールダイレクターを務め、本山雅志もアカデミースカウトとして日本中を走り回っている。エースFWだった高原直泰はJFL・沖縄SVのクラブ経営に携わり、彼と2トップを組んだ播戸竜二はWEリーグ理事など八面六臂の活躍を見せている。彼らの願いは「自分たちを超える選手・チームが出てくること」に違いないだろう。
「LINEグループがあって、イナ(稲本)が引退した昨年末にはみんなが『お疲れ様』とメッセージを入れていましたね。今もバン(播戸)が積極的に発信してくれていて、今年4月頃にも(小野)伸二と昌邦さん(山本=JFAナショナルチームダイレクター)と一緒に撮った写真などを上げていました。僕は見るだけですけど……(笑)。ワールドユースを戦っていた頃から『みんなサッカーに携わっていくんだろうな』とは思っていましたけど、本当にその通りになっていますね。
それぞれのタイミングややりたいことがあって、伸二やイナ、ヤットみたいに選手を長く続けた人もいれば、テッシー(手島)とか辻本(茂輝=池田市サッカー教室代表)みたいに早めに転身した人もいますけど、僕らが大舞台で決勝を戦った経験を今の仕事に生かさないといけないし、次世代に伝えていきたいと思います」
石川がしみじみとそう語る。当時、永井雄一郎(解説者)は「スペインだけはどうにもならなかった」とお手上げ状態だったと話していたが、シャビ率いる無敵艦隊に粉砕されたことも含めて重要な経験だ。
石川はファイナルのピッチには立てなかったが、ベンチから見たもの、感じたことにも意味がある。それを今の仕事に生かすことが、彼の使命に他ならない。(文中敬称略)
※第2回に続く
(元川悦子 / Etsuko Motokawa)

元川悦子
もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。