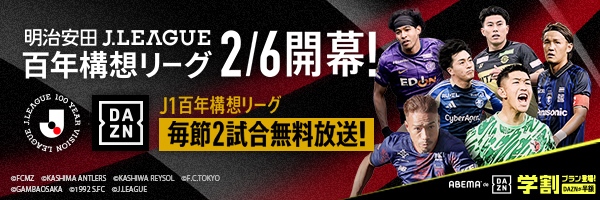Jリーグでの“連敗”が持つ意味 優勝チーム敗戦数で欧州と差…待たれるビッグクラブ誕生

欧州とJリーグで連敗が持つ意味を紐解く
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
町田ゼルビアの黒田剛監督は4月29日のJ1リーグ第13節でセレッソ大阪に2-1で勝利。連敗を3試合で止めたことを、ホッとした表情で振り返った。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
「自分自身としても、指導者人生でやっぱり慣れない経験というか、そういう意味でも、自分自身も成長するチャンスでもあった。こんな心境、気持ちになったのも初めてだったから、心の整理がつかなくて、常に不安で恐怖すら覚えたぐらい」
J1リーグ2年目の監督のセリフにしては、あまりに切迫しすぎているように思える一言だった。ただ、ヨーロッパのトップリーグを見ると、上位を狙うクラブにとって「敗戦」は特別なことだ。たとえば2024-25シーズンのプレミアリーグで優勝を飾ったリヴァプールは36試合を戦ってわずか3敗。スペインのラ・リーガで36試合を終えて1位のバルセロナから4位のアスレチック・ビルバオまでは5~6敗である。
ドイツのブンデスリーガでは首位のバイエルン・ミュンヘンと2位のレバークーゼンがそれぞれ2敗と3敗ずつ。イタリア、セリエAは36試合を終えた時点で首位ナポリは4敗しかしておらず、フランスのリーグアンで優勝したパリサンジェルマンに至っては33試合で2敗のみだ。
しかしJリーグを考えると、20チーム構成だった2024年シーズン優勝のヴィッセル神戸は8敗、18チーム構成の2023年の神戸は5敗、18チーム構成の2022年横浜F・マリノスが6敗と、ヨーロッパに比べると敗戦数が多いと言えるだろう。
もちろん2021年や2020年の川崎フロンターレのように2敗、3敗で優勝したチームもあるが、新型コロナウイルスの影響のなかった2019年を考えると横浜FMが8敗で優勝している。それだけJリーグのチームは拮抗した力を持っているということが言えるだろう。そのJリーグで連敗はどれだけの意味を持つのか。
森保監督もビッグクラブ誕生を要求
J1リーグが18チーム構成になった2005年以降、東日本大震災の影響で不規則なリーグ開催になった2011年、2ステージ制になった2015年、2016年、そして新型コロナウイルスの影響が大きかった2020年、2021年を除いて優勝チームがどれくらいの連敗をしていたかを考えると、対象の15シーズンのうちで連敗が一度もなかったのは5回のみ。
そして2回以上の連敗を経験して優勝したのは2005年と2014年のガンバ大阪だけ。4連敗以上(5連敗)を喫して優勝したのは2009年の鹿島アントラーズだけになる。ということは、15シーズンのうち7シーズンで優勝チームは2連敗か3連敗を一度だけ経験しているということだ。
つまり、現在のJリーグでは2連敗、3連敗を一度経験しても不安や恐怖を覚える必要はない。5連敗から優勝し、3連覇を達成した鹿島のようなチームもあるのだ。ただし、この現状は現状として、リーグのあり方としてこれでいいのかという問題が出てくる。
森保一監督はJリーグについて、「いわゆるビッグクラブが当たり前のように上位にいるヨーロッパのリーグとは違って、1位から20位までどこが勝ってもおかしくない、世界でも特別な戦いがある」としつつも、「予算規模が大きいチームにはビッグクラブとして結果も出していただいて、その中で中位、下位と予算で言うとそう分けられるチームが挑んでいくっていうリーグになってもいいかなとは思います」と感想を述べている。
国内でもっとはっきりとした階層ができて、「選手もよりビッグクラブにいき、タイトルをより可能性高く狙えるようなチームに行って、報酬も上がったり、知名度も上がったり、いろんなステータスも上がるっていうことがあってもいい」という考えだった。
浦和が予算規模でトップ
実際のところは、国内でもより大きなクラブに移籍するという動きはある。たとえばサガン鳥栖は昨シーズン途中に選手が浦和レッズや川崎などに移籍していった。予算規模の少ないクラブの性(さが)とも言えるが、さらに予算の違いが拡大していけば、このような選手がもっと多くなってもおかしくない。
現在Jリーグが公表している各クラブの経営情報で最も新しい2023年度版を見ると、J1(当時)の中でもっとも予算が少なかったのは鳥栖で年間売上が約25億円。最も大きかったのは浦和の約104億円と、すでに約4倍の差がある。
2022-23シーズンのプレミアリーグを見ると、マンチェスター・シティの売上高は約1000億円と言われており、売上高最下位のボーンマスとは約5倍の差がある。また、マンチェスター・シティ、マンチェスターユナイテッド、リヴァプール、トッテナム、チェルシー、アーセナルの6大クラブとその下は約2倍以上の予算規模の差がある。
もしも日本のサッカーがヨーロッパの歴史をなぞっていくならば、浦和がさらに規模を拡大し、その浦和についていくクラブと、その他に分かれてくるということになるだろう。
それはサッカーへの投資が大きくなっていくということで、悪いことではない。浦和の規模が10倍ぐらい大きくなって、同じくらい投資できるクラブが続々と出てくれば、日本に数多くの名手がやってくる。
そうなると、もう2連敗は許されない世界になる。世界のトップリーグの監督は一敗しただけでそんな恐怖心と戦っていることだろう。その心理状態を経験できるようになることが日本サッカーの強さにつながっていくのは間違いない。今回の黒田監督の言葉の切実さがさらに増すことは、日本の未来像なのだ。
(森雅史 / Masafumi Mori)

森 雅史
もり・まさふみ/佐賀県出身。週刊専門誌を皮切りにサッカーを専門分野として数多くの雑誌・書籍に携わる。ロングスパンの丁寧な取材とインタビューを得意とし、取材対象も選手やチームスタッフにとどまらず幅広くカバー。2009年に本格的に独立し、11年には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌で開催された日本代表戦を取材した。「日本蹴球合同会社」の代表を務め、「みんなのごはん」「J論プレミアム」などで連載中。