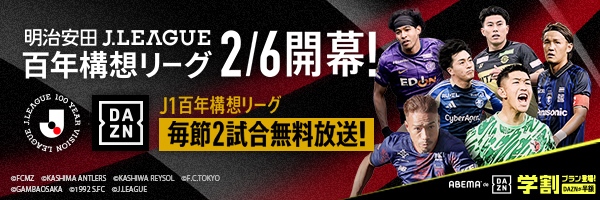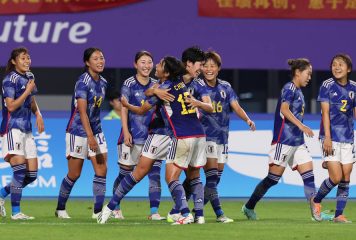アクセス、チケット代、観客動員…「FIFAに改善を」 クラブW杯で課題実感、“森保J”理想のシナリオ

シアトルはアクセスの利便性が抜群
世界の32クラブが参加し、アメリカの11都市・12会場で熱戦が繰り広げられている2025年FIFAクラブワールドカップ(W杯)。そのうち5つが1年後の2026年北中米W杯でも開催地となることが決まっている。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
その5会場とは、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム(メットライフ・スタジアム)、アトランタ・スタジアム(メルセデスベンツ・スタジアム)、フィラデルフィア・スタジアム(リンカーン・ファイナンシャル・フィールド)、マイアミ・スタジアム(ハードロック・スタジアム)、シアトル・スタジアム(ルーメン・フィールド)。
シアトルに関しては、浦和レッズが6月17日のリーベルプレート戦、21日のインテル戦の2試合を消化。本番の貴重なミュレーションの場となったのだ。
筆者は今回、そのシアトルに赴き、4試合を取材したが、6万9000人収容のルーメン・フィールドはアクセス面が大きなストロングポイントだった。広大なアメリカは車移動が基本で、鉄道では行けない競技場も少なくないが、ここはリンクライトレールの駅から徒歩圏。「スタジアム駅」と「インターナショナル・ディストリクト/チャイナタウン駅」のどちらからも徒歩10分以内という利便性が魅力である。
スタジアム駅からは元プロ野球選手のイチロー氏が活躍したシアトル・マリナーズの本拠地「Tモバイルパーク」の壮大な建物を眺めながら試合に行くことができるし、インターナショナル・ディストリクト駅からはチャイナタウンが近い。行き帰りにアジア食材店に立ち寄ったり、食事をする楽しみもあるだろう。
ライトレール(路面電車)の料金は全区間で1回3ドル(約450円)。近距離移動の場合、日本の2倍になってしまうが、交通系ICカードのオルカカードというものを3ドルで購入し、必要なだけチャージして使えるのは便利。しかも、モノレールやバスなど他の公共交通機関でも使える。料金を気にしなければ、日本にいるような感覚でスタジアムや町中、空港を行き来できるのはかなり有益だ。
スタジアム内は非常に見やすく、北側スタンドは独特の台形に近いデザインになっている。浦和サポーターが陣取ったのは南側だが、彼らが作り出した雰囲気を含め、会場の熱気というのは素晴らしかった。

W杯のチケット代は高額と予想
現地の人々のサッカー関心度も上がっている様子だ。地元のシアトル・サウンダーズが登場した15日のボタフォゴ戦は3万人、19日のアトレティコ・マドリード戦は5万人を突破したのだ。もともとシアトル・サウンダーズはMLS屈指の集客力を誇るクラブと言われ、1試合当たりの平均観客数が3万人を超えているのだという。そういったファンがクラブW杯を盛り上げに寄与したのは間違いない。
だが、浦和対リーベルは1万人強、浦和対インテルは2万5000人強とやや空席が目立った。前述のとおり、浦和サポーターの凄まじい熱量の応援は特筆すべきものがあったのだが、一般観客が少なかったのはやはり事実。今大会では、17日にオーランドで行われた蔚山HD対マメロディ・サウダウンズ戦が3412人、20日にオーランドで行われたベンフィカ対オークランド・シティ戦が6730人にとどまるなど、客足が鈍いゲームがいくつか散見されたのだ。
これは48か国出場の2026年北中米W杯でも懸念される点ではないか。欧州や北米・南米諸国の試合はアメリカ国民も興味関心を持って見るだろうが、それ以外の大陸の国々のゲームが全て満員になるとは言い切れない部分があるからだ。
今大会のチケット価格を見ても、浦和のグループリーグのゲームを例に取ると、50ドル(7200円)~500ドル(7万2000円)という幅広い設定で、決勝トーナメント以降はさらに高くなる仕組みだった。となれば、1年後のW杯も同等か、さらに高額になるはずだ。
アメリカ国内の急激なインフレと円安で物価が日本の約2倍になっている今、日本人の観客が誰でも気軽に現地に行けるわけでないし、似たような状況の国もある。カナダ・メキシコを加えた広大な3か国で開催されるW杯というのもハードルを引き上げる大きな要因だ。観客動員に関しては、多少なりとも不安が残ると言っていい。
一方で我々メディアを取り巻く環境に目を向けると、やはり課題がいくつかあった。まずルーメン・フィールドの記者席が室内にあり、メインスタンドの右コーナー側に寄っていたこと。クリケットスタジアムで代表戦がよく行われるオーストラリアでも似たような記者席を経験しているが、ガラスの窓枠が視界を遮ったり、角度的に見づらいといった難点があるのは確かだ。
1年後のW杯本番はメディアの数が爆発的に増えるため、メインスタンド中央に臨時記者席が設けられる可能性もあるが、現状のままではやや厳しいという印象だった。

FIFAが定めた取材環境はこれまでと一変
もう1つ注文したいのが、選手取材の環境。今大会は選手と直接話せるミックスゾーンの運用がかなり限定的になっていたのである。国際サッカー連盟(FIFA)が定めた取材ルールは、試合前日に登場する選手が3人、当日は4人のみ。浦和対リーベル当日は映像メディアとペン記者が一緒に囲みを行うという混乱状態に陥った。2戦目のインテル戦は浦和広報チームの努力もあって、登場選手が5人に増え、映像とペンが別になったが、全体に時間が短く、十分な質疑応答はできなかった。
過去のFIFA公式大会は、試合前日・当日のミックスゾーンには選手全員が通るという決まりになっていた。だからこそ、このルール変更には戸惑いの声が多く挙がったのだ。海外の場合、選手がミックスゾーンで全く喋らないケースが目立つため「確実に3~4人のコメントを取れるこの方式の方がいい」という意見も一部にはあるようだが、日本の取材陣としては受け入れられないものがある。
「1年後のW杯でもこんな形が続いたら、まともな取材はできない」と危惧する人も少なくなかったが、これは直視しなければいけない問題。FIFAには改善を訴えていくしかなさそうだ。
こういった課題はあったが、シアトルという町は治安が良く、6月の気温も10~25度と気候も爽やかで、快適だった。浦和の選手たちもピッチの芝の長さ以外はプレーしやすい環境だったのではないか。
とはいえ、ご存知のとおり、アメリカというのはとにかく広大な国。今大会中も猛暑や雷雨に見舞われた会場があったが、1年後の日本代表が必ずしも恵まれた環境で戦えるとは限らないのだ。
仮にポッド2を死守できたとしても、メキシコのいるA組だったら、メキシコシティ→アトランタ→グアダルーペという過酷な移動を強いられるし、アメリカのいるD組ならロサンゼルス→サンフランシスコ2試合と移動負担がかなり減る。カナダのB組なら、トロント→ロサンゼルス→シアトルと横移動も入って大変だが、気候的には比較的快適な中で試合ができそうだ。
どの会場でグループリーグを戦うのか。決勝トーナメント以降に移動や環境はどうなるのか。それが大会の成否を大きく左右する。そのことはチームもメディアもファン・サポーターも今一度、強く認識しておくべきである
(元川悦子 / Etsuko Motokawa)

元川悦子
もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。