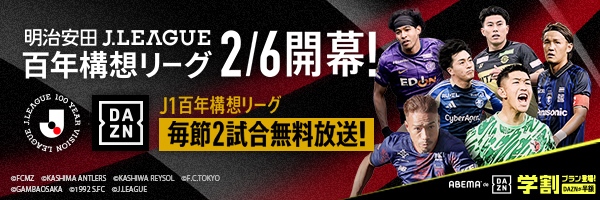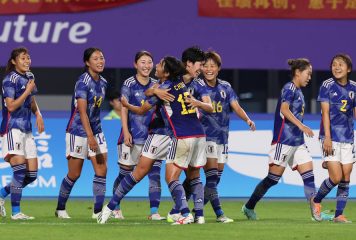高卒→即プロが抱える壁と“Jリーグ離れ”の現実 逆転の鍵を握る新リーグの真価

限られていた日本のポストユース年代の選択肢、U-21リーグ創設は必然
Jリーグが2026-27シーズンよりU-21リーグをスタートさせることになった。ポストユース年代(19~21歳)に適正なプレー(実戦)環境を提供し、育成強化を図るのだという。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
これまで日本のポストユース年代の選択肢は、基本的にプロか大学しかないと考えられてきた。だが高卒でプロ入りしても、すぐに出場機会を得られる選手は限られている。またJリーグを俯瞰しても、年功序列が染みついてきた多くの日本人指導者は、外国人監督に比べて若い選手の抜擢に躊躇する傾向が見て取れた。
その結果、三笘薫や武藤嘉紀らのように、高卒時点でプロで活躍できる可能性を示していても、慎重に大学へと迂回するケースが見られるようになり、逆にJクラブ側も心身とも熟した大卒選手たちを重用するようになった。
しかしポストユース年代は、最も急変貌の可能性を秘めた重要な時期である。特に世界の情勢を見れば、この大切な4年間を同じ環境で過ごすことが、一律に最適解でないのは自明の理だ。例えばブライトンで一気にスターダムを駆け上がった三笘もすでに28歳。もちろん大学で得た経験値も十分に貴重なのだろうが、選手としての資質を考えれば、最大限に可能性を開拓できたのかは疑問が残る。
こうして日本の育成最終段階の環境が未整備なのを、最も切実に感じ取るのは選手たちだ。だからこそ最近ではJリーグを経由せずに海外へ渡る選手が珍しくなくなった。もともと最近のサッカー少年たちの夢は、欧州のトップシーンで活躍することなので、早く現地に渡り順応するに越したことはない。しかも欧州のクラブならU-21チームもあり、提携クラブへの貸し出し制度も浸透しているので、実戦経験が減るリスクも少ない。「これでは有望株がJリーグに来なくなる」と関係筋が未来を憂うのも当然で、U-21リーグ創設は必然の流れだったはずだ。
ただしU-21リーグ創設は、1つの打開策だとしても、高卒選手たちの海外進出や大学志向に歯止めをかける劇的な即効性を持つとも思えない。何よりポストユース年代をJクラブで過ごすことが、海外や大学より高い確率で成功につながることが証明されなければ、選手は集まってこない。
Jリーグの新設リーグ、さらなる発展形を模索していくべき
もしU-21リーグが、ユースや高校のトーナメントと同様に同年代だけのタイトルマッチに終始するなら、あまり意味を持たない。日本サッカー界の課題は、学校単位の部活が軸を成した歴史が長く、同年代での公式戦が過密になっていることだ。本来なら高校チームの天皇杯挑戦への道を閉ざすくらいなら、インターハイや地域大会等を削減したほうが、選手育成の一助になったに違いない。
今回U-21リーグは、「必須」と「推奨」に分けてオーバーエイジ(OA)枠を設定。こういうルールを設ければ、国民性を鑑みても概ね「推奨」へと緩まるもので、場合によってはピッチ上に7人のOA(うち4名は24歳以下)が立つことが可能だ。
実は欧州や南米で若いスターが次々に誕生してくるのは、タレントの成長促進のために早めのタイミングで躊躇なく年上のグループに放り込んでいる背景がある。先日プレミアリーグ・フルハムのアカデミーに所属の高校3年生を練習参加させたAIE国際高校の上船利徳総監督によれば、Uー18年代の優秀な選手の過半数はすでにU-21やトップチームに合流しており、U-21チームで10番をつけてプレーしていたのは17歳だったそうだ。もちろんUー18でも試合をする以上は勝利を追求する。しかし最優先するのは、育成でありトップチームへの選手の供給という意識が徹底している。
育成の最終段階に入るU-21チームには多様な経験が必要だ。この時期の選手たちにとって最大の栄養となるのは、駆け引きやフィジカルに長けた大人との真剣勝負である。それは最近増えてきた10代でJ1に参戦中の選手たちの変貌ぶりを見ても明らかだし、ラミン・ヤマル(17歳FW/FCバルセロナ/スペイン代表)やデジレ・ドゥエ(20歳FW/パリ・サンジェルマン/フランス代表)らの痛快なブレイクは格好の手本となっている。武器を持つ選手たちは、異次元の環境に慣れてさえしまえば、加速度的に輝きを増していく。
Jリーグは新設のリーグを小さな塊の定期戦に止めず、天皇杯に挑戦させたり、大学との交流戦を設けたりするなど、さらに発展形を模索していくべきだろう。せっかくの施策がトップリーグの代謝と底上げを促進できなければ、その先には国内シーンの地盤沈下が待っているかもしれない。
(加部 究 / Kiwamu Kabe)

加部 究
かべ・きわむ/1958年生まれ。大学卒業後、スポーツ新聞社に勤めるが86年メキシコW杯を観戦するために3年で退社。その後フリーランスのスポーツライターに転身し、W杯は7回現地取材した。育成年代にも造詣が深く、多くの指導者と親交が深い。指導者、選手ら約150人にロングインタビューを実施。長男は元Jリーガーの加部未蘭。最近選手主体のボトムアップ方式で部活に取り組む堀越高校サッカー部のノンフィクション『毎日の部活が高校生活一番の宝物』(竹書房)を上梓。『日本サッカー戦記~青銅の時代から新世紀へ』『サッカー通訳戦記』『それでも「美談」になる高校サッカーの非常識』(いずれもカンゼン)、『大和魂のモダンサッカー』『サッカー移民』(ともに双葉社)、『祝祭』(小学館文庫)など著書多数。