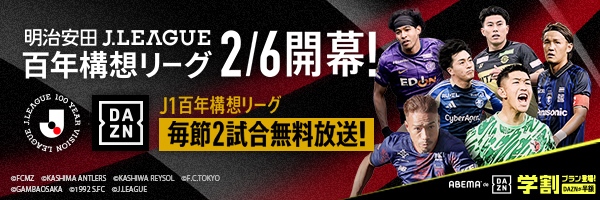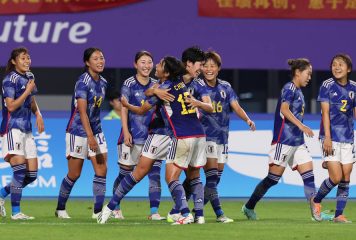上を目指す日本人選手へ「距離感が分かっていない」 元日本代表エースの忠告と“真実”

岡崎慎司の金言「プロになりたいって言っている子はたくさんいますけど…」
日本代表として119試合に出場し、歴代3位の通算50ゴールを叩き出した岡崎慎司。長年海外リーグでプレーしたエースストライカーは現在ドイツ6部チーム(FCバサラ・マインツ)で指揮を執るなか、上を目指す日本人選手について「ブレないでいられる芯」の重要性を説く。「本気でぶつかるところまではまだいってない」と語る岡崎の真意を紐解く。(取材・文=中野吉之伴)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
プロ選手は時間の使い方が大切だとよく言われる。チームの練習時間はさほど長くなく、自分の自由時間はそれなりにある。それを暇な時間と受け止めるのか、それとも自分への投資の時間と捉えるのかが将来を左右する大事なポイントになり得る。
「本気で取り組んでいます」と口では言う。その本気とはどんな覚悟で、何をしようとすることを言うのか。そこがブレてしまうとトップレベルで活躍するのは難しく、まして海外で活躍するのは限りなく困難だと思われる。
「いろんな刺激や誘惑があるなかでブレないでいられる芯を持っていたというのが自分にはあったのかな、と。今振り返るとそう思いますね。いろんな人がいるなかで、サッカーで成功したいっていう確固たる思いがあった。プロになりたいって言っている子はたくさんいますけど、例えばドイツの6部や5部でやっている選手が冬の中断期に日本に帰ったりする。仕事をしながらのサッカーっていうのは大変だと思う。でも、サッカーで何かを成し遂げるためにやらなければならないことに対しての距離感が分かっていない。その距離を埋めるだけのことをしていないし、本気でぶつかるところまではまだいってない」
岡崎の厳しい言葉だが、そこに真実がある。そしてこれは日本の育成年代全般についても言えることだろう。高い目標を掲げるのであれば、自分で今何をどのくらいやらなければならないかの考えを明確に持っていなければならない。
成長の矢印を自分に向けられるか「自分が大事なんですよね」
かつてボルシア・ドルトムントやレバークーゼンで活躍した元ドイツ代表MFゴンサロ・カストロがこんなことを言っていた。
「2部と1部の違いはスピード。特に思考のスピードだ。圧倒的に違う。考えてからプレーしていてはもう遅すぎる。常に次の、そのまた次の状況を予測して、選択肢を持ちながらプレーしていないと何もできない」
2部や3部はフィジカルコンタクトが多くタフなリーグというイメージが強いが、フィジカルコンタクトが多くなる1つの要因は判断スピードとプレー精度の不足だと指摘されている。目の前の局面をシンプルに回避する選択肢が少ないため、どうにか打開しようと競り合いが増える。それが1部のトップレベルでは逆転する。それこそ昨季ブンデスリーガ優勝のレバークーゼンは、フィジカルコンタクトができないほどスムーズかつスピーディーにボールを回し続けていた。
そこが到達点なのだとしたら、日本にいる間にフィジカルレベルや戦術理解度を高め、判断力を養い、ベストパフォーマンスのために日々のコンディション調整も不可欠だ。さらに将来的に海外でプレーしたいのであれば英語をはじめ、現地語の習得に時間を費やす必要もある。やるべきこと、やれることは多い。そうしたことと向き合うためには、成長の矢印を自分に向けられるかが鍵になると岡崎は語る。
「自分が大事なんですよね。まずは自分がちゃんとやっているかどうかって考えられるかが大事。環境や人のせいにしてしまうと、なかなか難しいなと思うんですよね、海外では特に。あれこれとサポートしてもらおうと思っていると厳しい」
とはいえ、岡崎自身もさまざまな失敗をしてきたと述懐する。そして失敗そのものが悪いわけではないとも説く。
「失敗はいっぱいしてきましたよ。例えばお酒を飲んでとか。そういう人付き合いもやってなかったら分からないこともあるので、経験すること自体は大事だったりする。でもどこかで気づくかどうかっていうのがすごく大事ですね」
岡崎が求める“基準値”「上のステージに行きたいなら…」
みんなでワイワイとやっている時は楽しい。人間は楽なほうに引っ張られてしまいがちだ。少し手を抜いても大丈夫だろうと考えてしまう時、派手な生活をしてみたいと思う時はあるだろう。それらに引っ張られすぎないように自制するのは簡単ではない。だが成し遂げたい何かを持っているのであれば、そうした自分の弱さを乗り越えなければならない。言われたからやるのではなく、自分で自分に打ち勝つ必要があるのだ。
「もちろんそれぞれが持っているキャパシティの問題なのかもしれないですけど、上のレベルに行く人が持っている基準値というのは確かにある。そこを伝えて、教えていきたいと思っている。上のステージに行きたいならこれくらいやるのが当たり前という基準値を知って、それを上手く生かして上に行く選手が増えてきてほしいなと思います」
世代のせいにしてはいけない。特徴に違いはあっても、成長するためにやらなければならないことは変わらないのだ。かつてイビチャ・オシム監督がジェフユナイテッド市原・千葉時代に1セッション4分のトレーニングを4分で終わらせたコーチを「サッカーの試合が4分きっかりで終わるのか!」と怒鳴りつけた話がある。
フィジカルや戦術理解をアップさせるためにスポーツ学の理論が必要で、身体や心を壊すような取り組みがNGなのは言うまでもないが、理論の遵守だけで成長につながるわけではない。ドイツ語で「指先の感覚」を持つことが大切と表現されるが、やらなさすぎず、やりすぎにならずの感覚を併せ持つ大人が、日本の指導者や保護者、サポーターにも増えてくることが望ましい。
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。