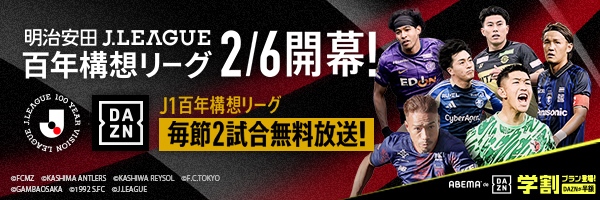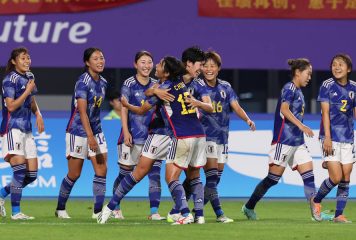Jと欧州で“直接商談”が可能「マッチングアプリみたいな存在」 移籍サービスの最前線【インタビュー】

日欧のサッカー界を熟知するモラス雅輝氏が語る、注目の移籍マッチングサービス
「日本サッカーの未来を考える」を新コンセプトに掲げる「FOOTBALL ZONE」では、現場の声を重視しながら日本サッカー界のあるべき姿を模索していく。現在オーストリア2部ザンクト・ペルテンでテクニカルダイレクター、育成ダイレクター、U-18監督を兼務し、日欧のサッカー界を熟知するモラス雅輝氏に、欧州の移籍市場で注目を集めている移籍市場電子化サービス「トランスファールーム」について聞いた。(取材・文=中野吉之伴)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
トランスファールーム(Transfer Room)というのをご存じだろうか。
1年に2度、様々なクラブのスポーツダイレクター、テクニカルダイレクター、チーフスカウト、ジェネラルマネージャーなどが集まる国際サミットが開催され、そこでダイレクトな情報交換をすることができる場所だが、行われるのはそれだけではないという。オーストリア2部ザンクト・ペルテンでテクニカルダイレクター、育成ダイレクター、U-18監督を兼任するモラス雅輝氏がその内情を説明してくれた。
「トランスファールームというのはいろいろやれることがあって、サミットで直接コンタクトを取ることもできるし、専用アプリを使って情報収集・交換をすることもできる。ものすごく乱暴に言えばマッチングアプリみたいな存在になるかもしれない。だけどすごく奥が深い。例えば国際サミットが開かれてもお互いのことがほとんど分からないまま、名刺交換だけで終わってしまうこともあります。ちゃんと準備をして、狙いを定めていかないと、お客様で終わってしまう。僕は国際サミットを通じていろんな方と知り合うことができたし、勉強にもなるし、さらにアプリを通じてコンタクトが取れて仲良く交流できてという発展が生まれるようになったのがすごくいいなと思います」
モラス氏が言うようにトランスファールームはここ最近、移籍市場電子化サービスとして欧州サッカーシーンで注目を集めている。
アプリ上で選手の情報交換やオファーを出し合うこともできるのだという。選手データを取り扱うサイトはたくさんあるし、どんどん詳細化されている。カメラを設置して試合映像を撮影するクラブが世界中で増えてきたことで、スカウトも現地へ赴く前に映像で相当入念な事前チェックができるようになってきた。トランスファールームではそうしたデータに加え、どのクラブが誰をどのくらいの値段で交渉準備ができているのかを知ることができる。トランスファールームと契約していれば、欧州クラブ間の直接交渉はもちろん、Jクラブも欧州や南米、北米など世界各国のクラブと直接のやり取りや交渉が可能だ。
「会員費を払って登録するんですね。クラブ単位でいくらだろう? 年間でうちは約200万円かかっていると思います。もちろん登録してもそれで選手が売れなかったら出費が増えるだけですよ。だけど、使い勝手はとてもいいと感じています。上手く利用したら、これまでだったら獲れないところから選手を獲ったり、いろいろできる。僕はすごくいいと思っています。朝ご飯を食べながら、このアプリの情報を見るのが日課になってますね」

トランスファールームのポイントは「代理人を通さなくても、というところ」
トランスファールームが生まれたのはデンマーク。当初からデンマーク国内だけではなく、ヨーロッパ全体をターゲットに作られた。ここ1~2年で一気に需要が伸び、利用を希望するクラブがどんどん増えてきているという。
発想の出発点は「どうすればクラブ間で直接やり取りがスムーズにできるだろうか?」だったという。今までは全部非公開でやっていたものを、ある程度オープンにして、お互いの交渉をもっと公正にしよう、クラブ間の情報交換をもっとスムーズに行えるようにしよう、という考えから生まれたものだ。
「ポイントは代理人を通さなくても、というところですね。選手の契約をする時に代理人は必要ですけど、クラブ間のやり取りの時は、むしろ自分たちだけで交渉したほうがスムーズなことが多いんです。これを活用しているエージェントもいるんですけど、限られた人しか参加できないようになっていると聞きました。参加人数全体の20%以下となっています。つまり国際サミットで会場に行くと80%はクラブ関係者ですね」
選手の移籍には代理人が間に入るのがサッカー界の常だが、誰もがフェアな取引を持ち掛けるわけではない。まだ世界的に知名度の低い選手をどうにか売り込もうと、あの手この手でアプローチをしてくる代理人がたくさんいる。それがためにこじれてしまうケースも少なくはない。自分たちがほしい選手にダイレクトにアプローチできたら、そのほうがクラブにとってはいい。
では具体的にどんな感じで使うのだろうか。
「例えばAという選手がいます。こちらから何万ユーロで、あるクラブにオファーを出してみるとします。もし興味あれば直接メッセージが来ます。その時に互いに値段交渉をすることもできる。毎日見てると、例えば『2週間前はベルギーのあるクラブが5000万円でFWを探してたけど、今、6000万円になっている。ということは、結構欲しいのか、適材が見つからないのかな』というのが見えてきたりするんですね。トランスファーサミットで直接会ってたりすると、相手がどんな人か分かるから、間に何人も通さなくてもいい」
あるトップチームで、突破力とクロスに秀でたサイドバックが必要という事情があったら、それに適合する可能性のある選手をこのアプリを通じて探し出し、ある程度のところまで「このくらいの値段で」という感触を最初から出し合うこともできる。
「例えば、獲得はできなかったけどあるU-20代表センターバックを見つけたりしました。コンタクトのきっかけを作ることができるし、あとで連絡も取れるのがいいですね」
バージョンアップ版で監督の情報も入手可能「将来的には監督だけでなく…」
また、これまでトランスファールームは選手だけが対象だったが、徐々に指導者も入っているという。
「バージョンアップしたものと契約をすれば、監督に関する情報も手に入ります。どこまでの情報化というと、例えばその監督が過去どこのクラブで指揮を執っていたかだけではなくて、例えば4-4-2システムをベースにプレッシング型のサッカーをする監督だとか、そういう詳細も出てきますね。その人が実際にどう指導するかまではさすがに分からないけど、もう5000人ぐらいの監督が確か登録されているはず。ただこれを使って監督を招聘したところはまだないとは思います。やっぱりデータだけでは分からないところもありますから、まだこれからという部分もあるでしょうね。僕としては将来的には監督だけではなくて、それこそ分析官やトレーナーとか、Jリーグだったら通訳とか、そうした人たちの情報も入れてあって、情報交換が円滑にできればいいなと思いますね」
使い方によってはネットワークの構築だけではなく、商談へつながる話も多くできるし、様々なクラブのチーム作りや移籍施策について知ることもできる。多くのスポーツダイレクターやテクニカルダイレクターが「トランスファールームの国際サミットに参加しています」というのをSNSでアップしたりするが、本当に存在するかどうかも分からない「関係者」がリークしては根も葉もない噂話がメディアやSNSに飛び交う時代に終わりを告げ、これまで以上に移籍のやり取りがクリアになってくるかもしれない。
「あ、トランスファールームで電話があった。あとで自転車でグラウンドに移動する時にコールバックします」
インタビュー中にそう言ってモラス氏は笑った。新しい時代の強化の仕事がそこにある。

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。