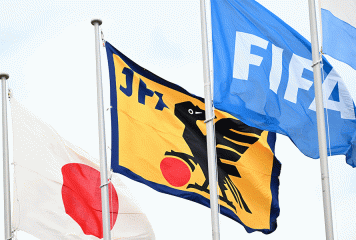「みんなスピーカーでも持ってるのか」完全アウェーの大熱狂 経験者が語る6年前の異様な空気【コラム】

敵地インドネシアは2018年のアジア大会、U-19選手権で10人が経験
11月の2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選・アウェー2連戦の一発目となる15日のインドネシア戦(ジャカルタ)が目前に迫ってきた。10日に森保一監督や長友佑都(FC東京)ら国内組が乗った航空機が羽田に引き返すというアクシデントに見舞われるなか、彼らは少し遅れて現地入り。欧州組も12日までに全員が到着し、27人揃ってトレーニングが行われている。
ご存知のとおり、今回はFW上田綺世(フェイエノールト)とDF谷口彰悟(シント=トロイデン)という攻守の要が怪我で不在。彼らがいなくても分厚い選手層で難局を乗り切れる強さを日本代表は示す必要がある。
【PR】ABEMA de DAZN、2/6開幕『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』全試合生配信!毎節厳選6試合は無料!
ただ、難しいのは現地への適応だ。11月のジャカルタは雨季の真っ只中。練習が行われる夕方は気温自体26〜27度とそう高くはないものの、湿度が90%に達することもある。しかも断続的に雨が降り、時にはゲリラ豪雨に見舞われることも。水を吸ったピッチはボールが止まったり、パスが思うように通らなかったりしがちだ。そこは細心の注意を払いながら戦わなければならないだろう。
加えて言うと、試合会場のゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムは約7万8000人収容で、当日は大観衆が押し寄せるという。インドネシアでの日本代表人気は高く、日本を応援するファンもいるかもしれないが、大半はインドネシアのサポーター。となれば、何か起きるたびに選手たちはプレッシャーを与えられることになる。「日本にリスペクトを持ちながらも、追い越してやろうという気持ちは強いと思う。チャレンジ精神に負けずにやる必要があるのかなと思います」と堂安律(フライブルク)も語っていたが、迎え撃つべきなのは目の前の敵だけではないのである。
日本にとってアドバンテージがあるとすれば、この過酷な環境を熟知している選手が少なくないこと。森保監督がA代表と東京五輪代表監督を兼務して、初めての大舞台となった2018年のアジア大会もインドネシア開催だった。DF板倉滉(ボルシアMG)、MF三笘薫(ブライトン)、旗手怜央、FW前田大然(ともにセルティック)の4人は当時のメンバー。ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムで試合はしなかったものの、現地の雰囲気や感覚を知り尽くしたうえで試合に入れるのは大きい。
さらに、そのアジア大会の2か月後に行われた「AFC U-19選手権2018」のメンバーも何人かいる。それはMF久保建英(レアル・ソシエダ)、DF橋岡大樹(ルートン・タウン)、菅原由勢(サウサンプトン)、瀬古歩夢(グラスホッパー)、GK大迫敬介(サンフレッチェ広島)、谷晃生(FC町田ゼルビア)の6人で、大迫と瀬古を除く4人は、U-20W杯出場権のかかった準々決勝に先発。6万人のインドネシアサポーターが押しかけ、土砂降りの雨が降りしきるなか、東俊希(広島)と宮代大聖(ヴィッセル神戸)のゴールで2-0の勝利を手にした経験をしている。
久保は当時、「本当に(試合の)最初はみんなスピーカーでも持ってるのかってくらい(の大声援)だった。日本の応援とは違って、みんながみんな声がデカいし、どこがゴール裏か分からないくらい声がデカかったですね」とコメントしていたが、日本では感じることのできない異様な熱気に包まれたのは紛れもない事実だ。
立ちはだかる大観衆と雨「8万人もお客さんがいれば声は通らない」
それを実体験していた菅原は12日の練習後に「マジで懐かしいですね。6年前か。なんかいいっすね、ジャカルタって感じですね」と笑顔を見せ「僕らの時も大アウェーというか、インドネシアの圧力がすごくあったと思うんですけど、アウェーの方が僕ら選手も気持ちも上がる。ああいうアウェーの中でこそ、『俺たちは絶対に勝つんだ』という気持ちにさせられた。あの雰囲気があったからこそ、ああいう難しい試合でも勝ち切れた。インドネシアのサッカー熱はすごかったですけど、そういう熱があった方が気合いが入ると思うので、試合がすごく楽しみですね」と、しみじみと語っていた。
菅原や久保、瀬古、谷ら2000年世代は、森山佳郎監督(現ベガルタ仙台)が率いていたU-15日本代表の最初の海外遠征でもインドネシアに訪れている。「今の日本の若い世代は人工芝ピッチなど整ったグラウンドでしかプレーしたことがない。だからこそ、あえてドロドロのピッチでグチャグチャになりながら戦う経験をしないとダメなんだ」と当時、指揮官は語気を強めていたが、そうやって過酷な環境を乗り越えてきた経験は大きい。その積み重ねが、6年前のU-19インドネシア戦勝利の原動力になったと言っても過言ではない。
とはいえ、土砂降りの雨の中、大観衆の下でプレーするとなれば、試合運びの難易度は間違いなく上がる。
「8万人もお客さんがいれば声は通らない。普段からそういう状況ではやっていますけど、より細かいところですり合わせを練習からやっていく必要があると思います。うまくいかない時間帯もあるかもしれないけど、自分たちがしっかり耐えることが肝心。チーム一丸となって戦うことが大事だと思います」
6年前の経験者の1人である大迫もこう語っていたが、微妙なズレが致命傷にならないとも限らない。特に今回は谷口不在で最終ラインが変則的な構成になる。これまでの最終予選4試合とは異なる感覚でプレーせざるを得なくなるため、密なコミュニケーションが必要不可欠だろう。
それは6月のミャンマー戦(ヤンゴン)以来の先発が有力視される橋岡も重々承知している部分。2018年のインドネシア戦で最終ラインを統率し、MVP級の働きをした彼は「僕たちはずっと大観衆の浦和レッズでやっているので、そこはほかの人より慣れているんじゃないかなという気持ちもありました。途中から雨も降ってきて、少し視界が見づらくなってきたなかでも集中を切らさずにできたんじゃないかと思っています」と胸を張っていた。その記憶は本人にとっても鮮明に違いない。その再現を同じピッチで見せられれば最高のシナリオ。今回は貴重な経験値を遺憾なく発揮すべきなのだ。
インドネシアに苦戦しているようでは、2026年W杯優勝という目標には手が届かないだろう。「やっぱり日本は強かった」と現地の人々が感心するような圧倒的な強さを示し、3ポイントを獲得すること。それは今回の日本代表に課されたノルマだ。インドネシアを経験している若い久保や橋岡らが、その牽引役になってくれれば理想的である。
(元川悦子 / Etsuko Motokawa)

元川悦子
もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。