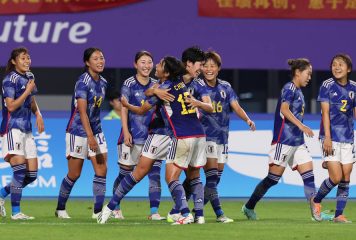中田英寿が示した日本人初の“世界基準” 「シャツ」の蔑称も…語学とプレーで英国に刻んだ記憶【現地発コラム】

キャリア最終年に英国の地で刻まれた“NAKATA”の名前
名プレーヤーを数多輩出してきた日本サッカー界にあって、日本代表や欧州クラブで輝かしい実績を残した中田英寿氏はその代表格の1人だ。ワールドカップ(W杯)3大会に出場したレジェンドは早くから世界に目を向け、21歳でイタリア1部セリエAへの挑戦を決断し、サッカーの母国イングランドでもプレーした。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
2006年夏に29歳で現役を引退した「孤高の天才」は、一体どんな人物だったのか。「FOOTBALL ZONE」では改めてそのパーソナリティ-紐解くべく中田氏の特集を展開。今回は短いながらも濃密なプレミアリーグでの現役ラストイヤーを振り返る。(文=山中 忍)
◇ ◇ ◇
中田英寿のイングランド時代は、2005-06シーズンのみ。しかも、現役最後のシーズンだった。
2005年8月18日のボルトン入団会見から、翌年5月7日のプレミアリーグ最終節バーミンガム戦(1-0)までの約9か月間、イングランドにおける「ボルトンの中田」報道では、「マーケティング」と「クオリティー」の二語が印象に残っている。
当時はまだ、日本代表選手が「サッカーの母国」で「サッカー後進国」の選手という目で見られていた時代。獲得に動くイングランドのクラブには、チームパフォーマンスよりも、経営パフォーマンスの改善という動機があるとの見方が強かった。
巷では、日本人選手が陰で「シャツ」と呼ばれてもいた。予想される貢献は、レプリカシャツの売り上げを伸ばし、日系企業とのスポンサー契約を増やすこと。ピッチ外での存在感だけに注目するネガティブな視線を浴びていた。
日本人挑戦者たちが、そうした先入観を打ち消せずにいたことも事実だ。フィオレンティーナから期限付き移籍でやって来た中田は、イングランドにおける通算5人目の日本人選手。2001年に先陣を切った稲本潤一(現南葛SC)は、名門アーセナルの選手としてプレミアのピッチに立つことがなかった。同年にボルトン入りの西澤明訓も同様。川口能活は、ポーツマスがプレミア昇格を決めた2002-03シーズンを最後にデンマークへ。戸田和幸は03年1月に加入したトッテナムでリーグ戦出場も果たしたが、半年間の短期逗留に終わった。
現地メディアは、日本市場における中田の“商品価値”が、先達の4人を大きく上回ることを認識していた。その2、3年前までは、イングランドの人々も内心では名実ともに「格上」と認めざるを得なかったイタリアのトップリーグで実績を残した日本人だったからだ。そこで中田は、「祖国でベッカムよりも多くレプリカシャツを売ったスター」という目で眺められもした。
実際、ボルトンがプレシーズンの日本遠征中ではなく、前シーズン終了直後から獲得に本腰を入れていれば、即座に帳簿上での効果が確認されていたことだろう。2005年夏に行われたJリーグ勢との親善試合は、2試合とも数千人程度の入り。総売上も5000万円を下回った。これが「中田のいるボルトン」の遠征であれば、軽く数倍の観客動員数と関連収入につながったことは想像に難くない。
もっとも、中田はピッチ上でも即戦力と目されていた点で、彼に先立つ日本人4選手とは違っていた。1999年からのサム・アラダイス体制下にあったボルトンは、別名「キャリア再生工場」。そこは、大物ベテランを輝かせ、ひと癖ある一線級をその気にさせる新任地だ。28歳で加入の中田は後者のカテゴリー。パルマ、そしてフィオレンティーナでも指揮官との意見対立を見たチェーザレ・プランデッリ体制から解放される格好での移籍だった。
新レギュラーとして中田の蘇生が叶えば、斜陽の感が否めなくなっていたテクニシャン、ジェイ=ジェイ・オコチャからのバトンタッチが可能になる。さらに言えば、先代の外国人ヒーロー、ユーリ・ジョルカエフばりの影響力をも期待されていた。元フランス代表の攻撃的MFは、30代で移籍した2002年に降格回避の原動力となり、続く2シーズンも主軸として過ごしたアラダイス体制下での成功を象徴するワールドクラスだった。
語学力とプレーで示した“世界基準”の能力
中田自身も、お披露目会見の席で「テクニカル・プロブレム」という表現で監督との衝突を一因として挙げつつ、「サッカーの喜びを見失っていた」ことを認めていた。このイングランド報道陣を前にした第一声により、英語の使い手としても「中田は違う」との印象を与えもした。
筆者には、中田のイタリア人代理人と親しいイングランド人の仕事仲間がいた。本人とも会っている彼は、「あんなに英語が上手いのなら、英会話なんて習わなくていいのに」と言っていた。頭脳明晰なオックスフォード大卒で、日本語が流暢なこともあって外国人の英語にはうるさい彼が、「ヒデの英語はすごく自然だ」と褒めていたことを覚えている。
セリエA時代から英語を学んでいた努力もさることながら、イタリア語も身につけた生来の語学センスと、言語を含めて異国の環境に溶けこうとする積極姿勢の為せる業だと言える。
中田は、リーボック・スタジアム(現タフシート・コミュニティ・スタジアム)の会見場で、「どこにいるのかを理解すべき」だとして日本の報道陣にも英語を要求した姿勢でも、英国記者陣から一目置かれた。日本語禁止の背景に、祖国メディアとの不仲もあったことは承知している。とはいえ英語圏メディアで、大衆紙と高級紙の別を問わず「ほぼ完璧な英語」だと報じられていた。
最も肝心なプレミアのピッチ上でも、“世界基準”の能力は確認された。初のマン・オブ・ザ・マッチ選出は、第7節ポーツマス戦(1-0)。前節後半にベンチを出てデビューを果たした翌週、移籍後初先発でのことだ。ボルトンでの初ゴールは、第10節ウェストブロミッジ戦(2-0)。ゴール右約17メートルの位置で自ら奪ったFK(フリーキック)を左下隅にカーブをかけて蹴り込んでいる。中盤中央で並んだケビン・ノーランが決めた2点目も、コーナーフラッグ付近でルースボールをものにした中田のプレーに端を発していた。
ウェストブロミッジを率いていたブライアン・ロブソンは、中田が決めたFKを与えた主審の判定を敗因に挙げていた。しかし、ボルトンの勝因は自軍に味方した判定ではなかった。それは、ビジョン、テクニック、ハードワークを兼ね備えた味方の一員、中田の存在だった。
疲れた心を癒すには至らなかった2000年代半ばのイングランド
ところが、この初ゴールはボルトンでの全32試合出場で唯一の得点となってしまう。プレーメイカー志向の策士にとって、当時プレミアの非強豪クラブは、サッカーの喜びを噛みしめられる環境とまではいかなかった。
個人的には、中田の初ゴールと同時期に凶兆を目撃したような気がしていた。ボルトンが西ロンドンに乗り込んだ第9節チェルシー戦(1-5)。開始早々に先制した前半から、数少ない相手ゴールへの脅威はクロスを含めて空中からもたらされていた。ハーフタイムを境にボルトンのベンチを出た中田は、試合の流れがスコアにも反映された後半、合わせて敵の3得点に絡んだMFフランク・ランパードとは対照的に存在感が薄かった。
ロンドン市内南東部でのチャールトン戦(0-1)は第11節。ボルトンは、勝ち点「3」を国内北西部に持ち帰ってはいる。中田も、最初で最後となるアシストを記録した。だが、ノーランによる決勝点のお膳立ては、味方のロングシュートがセーブされたリバウンドをゴール至近距離で折り返したシンプルなもの。ボルトンの攻撃は、中盤がバイパスされるケースが多かった。
シーズン後半戦の中田は、欧州大陸経験者として期待されたUEFAカップ(現ヨーロッパリーグ)で、32強敗退となったマルセイユ戦2試合(計1-2)のピッチにいなかった。プレミアでもベンチ外が8試合。最終節では後半早々にオコチャとの交代でピッチを降り、その2か月後にはスパイクを脱ぐことになるのだった。
29歳での早過ぎる引退は、主将を超えた代表の「顔」としての心労も一因だったに違いない。W杯ドイツ大会で日本のグループリーグ敗退が決まった翌日、チームホテルの受け付けで偶然隣にいた中田。額のニキビが、「エンジョイ」という言葉とは正反対の「ストレス」を思わせた。
ボルトンの指揮官は、中田の在籍2シーズン目を望んでいた。ファンも、そして国内メディアも、2年目のイングランドでシーズンを通じた本領発揮を楽しみにしていた。引退を告げた公式声明によれば、当人はイングランドでのシーズン後半に意を固めていたことになる。
プレミア復帰5年目を8位で終えることになったボルトンが、例えば、プレミア昇格5年目の一昨季を9位で終えたブライトンのようなチームだったとしたら? 当時のプレミアが、パスサッカー路線の中小クラブも珍しくはないリーグだったとしたら? 中田のようなタレントは、疲れた心を癒すだけの喜びをピッチで実感することができたかもしれない。
そして中田に対する最終的なイングランドの記憶は、トップクラスの片鱗を窺わせた日本人選手というレベルを超えていたはずだ。サッカー好きな庶民の眼前でも、サッカーの楽しさを体現したトップクラスとして。
山中 忍
やまなか・しのぶ/1966年生まれ。青山学院大学卒。94年に渡欧し、駐在員からフリーライターとなる。第二の故郷である西ロンドンのチェルシーをはじめ、サッカーの母国におけるピッチ内外での関心事を、時には自らの言葉で、時には訳文として綴る。英国スポーツ記者協会およびフットボールライター協会会員。著書に『川口能活 証』(文藝春秋)、『勝ち続ける男モウリーニョ』(カンゼン)、訳書に『夢と失望のスリーライオンズ』、『バルサ・コンプレックス』(ソル・メディア)などがある。