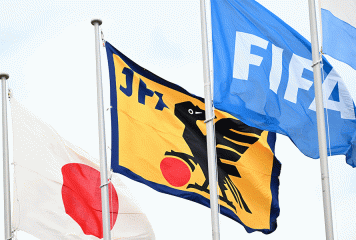名将就任で「良さを見失っていた」 囚われた10番の重圧…復活のカギとなった“割り切り”の美学

西野朗監督の要求、ファンタジスタに苦悩
名古屋グランパスの黄金期を支え、現在は指導者としての道を切り拓く小川佳純氏。2025年度に取得したJFA Proライセンスのため、海外研修の一環でベルギー1部シント=トロイデンVV(STVV)を訪れた。現地で「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じ、13年間のプロ生活で培った勝負師の顔と、引退後に目覚めた戦術家としての顔を見せた。連載の第3回は、名将・西野朗との邂逅、背番号10の重圧と「割り切り」の美学について。(取材・文=FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞/全5回の3回目)
【PR】ABEMA de DAZN、2/6開幕『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』全試合生配信!毎節厳選6試合は無料!
◇ ◇ ◇
名古屋グランパスで転機が訪れた。小川氏はピクシーことドラガン・ストイコビッチ監督とともに2010年のJ1リーグ初制覇を経験。理論的なタスクを与えられ、完璧に遂行することで黄金期を彩った。そんななか、2014年に最大の変化が訪れた。のちに日本やタイの代表監督を務める西野朗氏の名古屋監督就任だ。
ベルギーの地、シントトロイデンで当時を振り返った小川氏。その言葉にはプロとして生き抜くための“狡猾さ”と“自己客観性”の重要性が凝縮されていた。
「西野さんは、それまでの監督たちとは真逆で、非常に自由度が高く、選手に多くを委ねる方だった。ピクシーまでは『ここに立ちなさい』という明確なポジションと役割があって、自分はそれを表現することに長けていたと思う。だからこそ、自由は逆に戸惑いがあった。何をしてもいいと言われた時に、周りと合わなかったり、自分一人で局面を打開できなかったり……。スタメンを外れる試合も増え、自分に対してイライラし、悔しさを抱えていましたね」
当時の小川は「背番号10」を付けていた。伝統ある10番。小川は悩んだ。かつてガンバ大阪でJリーグ、アジアの優勝を経験した西野監督がイメージする“10番”は元日本代表MF二川孝広のようなファンタジスタではないか。オン・ザ・ボールでゲームを組み立て、攻撃に魔法をかける——。要求を汲み取った。
「西野さんが僕に求めている像がわかった時、自分もそれに応えようと必死だった。でも、僕は本来ボールを持ってリズムを作るタイプではなくて、オフ・ザ・ボールの動き出しで勝負するタイプ。得意ではないゲームメイクを無理にやろうとして、自分の良さを見失っていた。10番という番号に囚われ、理想と現実の乖離に苦しんだ」
辿り着いた“引き算”の思考「得点が取れる場所へ」
もがき続けた西野体制の1年目を経て、小川は1つの「割り切り」に辿り着いた。プロとしての寿命を延ばすことになる“弱点の隠蔽”という戦略だった。
「西野さんの2年目、ようやく自分の良さを取り戻すことができた。『10番だから真ん中にいてゲームを作らなければいけない』という固定観念を捨てたから。苦手なことを克服して完璧な選手を目指すのではなく、苦手なことはほかの選手に任せて、自分は一番の武器である『得点が取れる場所』へ顔を出し続けることに特化しようと決めたんです」
“引き算”の思考は功を奏した。オン・ザ・ボールでの創造性に囚われず、味方の状況を見て裏に抜け出し、相手の逆を突いて背後を取る。本来の強みを、西野監督の自由なサッカーの中で再構築した。
「プロの世界で長く生き残るためには、すべてを自分でこなそうとしないことも1つの技術。苦手なことを無理にさらけ出す必要はない。一種の割り切りというか、自分の仕事ができる場所を見極める力が身についた時期だった」
2016年限りで10年間過ごした名古屋を離れ、17年からサガン鳥栖へ新天地を求めた。新たな環境に身を置き、新たな出会いもあった。当時32歳だった小川が衝撃を受けたのがプロ3年目の若手、現在プレミアリーグで活躍する日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)だった。
「大地は、本当にいい選手だった。若いのに不貞々しいというか(笑)。自分の良さを絶対的に信じていた。僕が1年目に(名古屋で)一緒にプレーした本田圭佑と同じ空気を感じた。20歳で豊田陽平にも要求が激しかったし、物怖じしない。でも、プレーが伴っているから誰も文句は言わない。とんでもないやつだな、と。彼らのような選手に出会えた経験も今となっては良かったです」
様々なスタイルの名将、強烈な個性を持つチームメイト。小川は常に自分と異なるものを受け入れ、自分の良さをどこに当てはめるかを模索し続けてきた。その柔軟性と、自らを冷徹に分析する眼差し。13年間のプロ生活で円熟味が増した1つの理由だった。
(FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi)