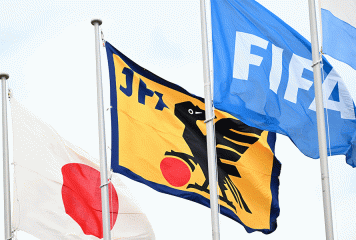16歳でW杯デビューし猛勉強で国立大に進学 科学トレーニングで世界とたたかう身体に

16歳で日本代表デビュー たった5分の出場時間が選手人生を変えた
三菱重工浦和レッズレディースのFW安藤梢。2011年の女子W杯優勝メンバーで42歳の今も現役を続けている。その人生を大きく動かした原点は16歳で経験したW杯の舞台だという。文武両道を貫き、世界の頂点と学びの現場を知るレジェンドが、「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューに応じた。さまざまな経験を経て、女子サッカーの未来に託す想いについて語った。(取材・文=FOOTBALL ZONE編集部・砂坂美紀/全3回の2回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
安藤梢は文武両道の人だ。小学6年生で全国制覇したものの中学には女子チームがなかったため、男子サッカー部で1人だけ女子選手としてプレー。レギュラーを勝ち取り、成績は常に学年トップクラスをキープ。「負けず嫌いな性格で、スポーツと勉強の両方で1番を取りたかったから」と安藤は笑うが、並大抵の努力ではなかった。
高校は地元屈指の進学校・栃木県立宇都宮女子高に入学。1999年のアメリカW杯(FIFA女子世界選手権)の日本女子代表のメンバーにも選ばれた。
16歳の安藤は夢舞台のベンチに座り、「試合に早く出たくてうずうずしていました。自分はできる。私が出たら絶対活躍するのに、って生意気にも思っていました」と、その時が訪れるのを心待ちにしていた。声がかかったのは、グループステージ3戦目のノルウェー戦の後半41分のことだった。
「ピッチに入って最初にぶつかっただけで、もう過呼吸になって。それから終了までずっとヘロヘロで、自分のプレーを全く出せませんでした。もう大人と子供のようで、フィジカル的に全然戦えないし、技術も出せない。世界との差を知って、衝撃でした」
前回W杯優勝国相手に0-4と日本のグループステージ敗退が濃厚になったところでの起用。当時の宮内聡監督が与えた約5分間は彼女を変えるには十分な時間だった。持ち前のドリブルやスピードで勝負できなかった記憶が進路を明確にした。
「大学でスポーツ科学のことを学んで、自分が世界で戦えるようなフィジカルの選手になりたいと思いました」
猛勉強の末に、井原正巳や中山雅史らを輩出した、筑波大学へ進学。スポーツ科学を学び、サッカーに必要なフィジカルトレーニング、陸上の専門家にスプリントをみっちり身に付けた。入学直後は筑波大学の女子サッカー部に所属したが、代表落選を経験したこともあり、2002年に当時のトップリーグ、L・リーグ(日本女子サッカーリーグ)のさいたまレイナス(現・三菱重工浦和レッズレディース)に入団。
大学の研究室では『チーム梢』を結成して、さらなるトレーニング強化と栄養の専門知識などをエキスパートから学んで肉体改善に取り組んだ。210キロものバーベルで負荷をかけてスクワットしたり、5メートルを1秒で走り切るスプリントをしたり、最新の科学トレーニングに明け暮れた。すると、相手を置き去りにするスピードと当たり負けしない強靭な身体を手に入れ、ユニフォーム越しにも鍛え上げられた筋肉が分かるほどの後ろ姿が異彩を放っていた。
約9万人の観客が集まったW杯決勝に憧れ 国内リーグ優勝、得点王、MVPを置き土産にドイツへ移籍
国内リーグでは新人賞を獲得したのを皮切りにクラブのエースに君臨し、FWとして得点を量産。なでしこジャパンでも欠かせない存在となり、2度のW杯と五輪に出場。とくに2008年の北京五輪ではメダルまであと一歩という4位になったことで、その目は自然と世界に向いた。
かつて16歳で経験したW杯、開催国のアメリカの女子サッカー人気を体感したことが、さらなる大きな夢を描く原動力となっていた。
「実は、あの時から海外でプレーしたいってずっと思っていました。(1999年女子W杯の)アメリカと中国の決勝は、9万人ぐらいの観客が入っていて、『女子サッカーにそんな世界があるんだ!』って、すごく驚いて。いつか日本もそうなりたいという夢を持っていました。澤(穂希)さんがアメリカでプレーして活躍していたのも、すごく憧れていました」
浦和レッズレディースには2009年のリーグ優勝、得点王、MVPを置き土産に、2010年からドイツ・女子ブンデスリーガの強豪チーム、FCR2001デュースブルクへの移籍を決めた。筑波大学の大学院に籍を置き、博士課程を目指していたなかでの決意だった。
「ドイツ代表が何人もいるような強いチームで、最初は衝撃を受けました。毎日の練習でも、(マッチアップした相手に)吹き飛ばされていましたから。それに、日本とヨーロッパのサッカーが全然違うので、その中に適応していくのはすごく難しかった。もちろん、合わせていく部分もあるけど、自分らしさも出していかなきゃいけないので大変ですが、貴重な経験でした」
ドイツは2003年と2007年の女子W杯2大会連続優勝の絶対王者。その代表選手である、FWインカ・グリングスやFWアレクサンドラ・ポップらが所属していたデュースブルク。安藤が移籍したのは、日本がワールドカップで優勝する前年であり、なおさら難しさを感じた。
「日本にいた時は、自分がフォワードで、みんなが私にタイミングを合わせてボールを出してくれたけど、そんなのは絶対にないですし。パスがまずもらえないし、『もっとこのタイミングで欲しい』と言っても、『いや、それは日本のサッカーでしょ。ドイツは違うから』みたいな感じで言われて」
初めての海外移籍で「この中で生き残ってかなきゃいけない。どうしたらいいんだろう」と、壁にぶつかった。自己主張をしなければ置いて行かれる世界で、アピールを続けた。
「なんとか生き残るために必死で。中心選手のインカ(・グリングス)がトラップミスしたボールを拾ってゴールすると、みんなが次からパスくれるようになったこともありましたね。試合に出られない時もあったけど、チャンスでしっかり結果を出して。生き残っていくには、このポジションは嫌だとか言っていられないので、何でもやりました」
持ち前のスピードや決定力に磨きをかけて、臨んだ2011年のドイツW杯。準決勝でなでしこジャパンはドイツ女子代表と対戦。安藤はFWでスタメン出場して、攻守に渡って貢献した。延長後半、丸山桂里奈が決勝点を挙げて1-0でドイツに勝利。その勢いのまま日本は勝ち進み、世界一となった。開催国であるドイツ中が注目していた大会で躍動する日本の戦いぶりに、それまでの扱いを一変させた。
「全く変わりましたね。デュースブルクで急に『日本のサッカーをやろう、コズエ』『美しくパスを繋いでみたい』って、(マルティナ)フォス監督が言い出して(笑)。世界一になるってすごいですよね。特に、ドイツはサッカーの人気がとても高い国だったので、、急に評価が変わって驚きました」
のちにドイツ女子代表監督となるフォス監督だけではなく、なでしこのサッカーが世界の女子サッカーのトレンドを変えた。安藤は「アメリカ代表もショートパスを使い出したし、どの国も取り入れ始めました」そういって、歴史の転換点になった当時を振り返る。
翌年には2012年のロンドン五輪で銀メダル獲得にも安藤は貢献。デュースブルクの経営不振の影響もあり、2013年に1.FFCフランクフルトへ移籍。UEFA女子チャンピオンズリーグ制覇も経験した。2017年に筑波大学の大学院で博士号を取得するために帰国して、古巣の浦和Lへの復帰を発表した。
「レッズからドイツに移籍するときに、『帰ってくるのを待っている』ってサポーターのみなさんに言われていたので戻りました。日本で自分のプレーを見てもらいたいという気持ちもあって、待っていてくれて嬉しいですね。ドイツで成長した部分をまたクラブの中で貢献していきたい、という思いがすごくありました」
世界の頂点に立ったからこそわかる 日本の女子サッカーとWEリーグに必要なこと
世界、欧州の頂点に立った彼女だからこそ、日本で感じることがある。結果を残すことで評価が変わるのは世界共通であることだ。日本ではなでしこジャパンがW杯で優勝後、なでしこフィーバーが巻き起こった。当時のトップリーグ、なでしこリーグに1万人を超える観客が集まったこともあった。
「代表が結果を残すと、女子サッカーが爆発的な人気になるんですよね。それを、身を持って体験したからこそ、代表の結果は大事。あのころの代表メンバーと『どうやったら女子サッカーがもっと盛り上がるだろうね』という話にもなります」
イングランドも2022年のUEFA欧州女子選手権(女子ユーロ)で自国開催で優勝したのをきっかけに女子サッカーの人気が高まり、今年も女子ユーロ連覇を果たすとさらなる盛り上がりをみせている。
日本初の女子サッカープロリーグのWEリーグが発足して5年、昨季は2万人を超える集客を果たした試合もあった。安藤は期待を込めて未来を予測する。
「今は、本当に女子サッカーのレベルがすごく上がっていると思う。一緒にプレーしていても、若い選手たちの技術も高いです。私の時はサッカーをしている女の子が全然いませんでしたが、今は多くなりました。日本の女子サッカーのレベルもすごく上がっているけど、海外のレベルの方が高いとは感じますね。だから、海外でプレーした選手が成長して、WEリーグに帰ってきてレベルを上げて、若い選手の成長を促して、将来的になでしこが強くなって還元されていくのがいいのかな、と思ったりします」
16歳で世界との差を感じ、その壁を自らの力で乗り越えてきた安藤。日本に戻ってきても、大きな存在感を放っている。彼女が走ってきた道のりを、多くの後輩たちが続いて、日本の女子サッカーをより発展させてくれるに違いない。
(砂坂美紀 / Miki Sunasaka)