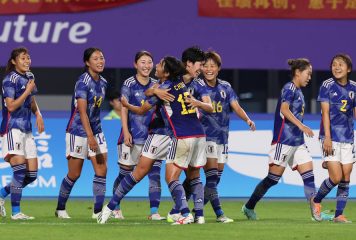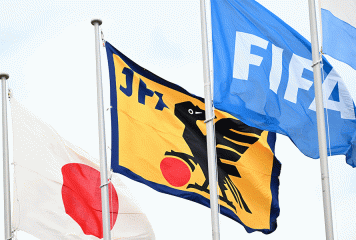監督の注文を“まさかの拒否”「やりたくない」 現役日本代表が見せた強いこだわり「痛感させられた」

四方田修平氏が語る小川航基「チームのやり方と航基のよさがマッチした」
北海道コンサドーレ札幌で手腕を発揮した四方田修平監督(現大分トリニータ)が横浜FCの指揮官に就任したのは2022年。23年という人生の半分以上を過ごした北海道を離れ、幼少期を送った横浜へ戻るというのは、やはり大きな決断だったに違いない。(取材・文=元川悦子/全7回の5回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
当時、横浜FCは2年間在籍したJ1からの陥落が決まり、再昇格に向けてチームを再構築しようとしていたところだった。四方田監督は伸び悩んでいた小川航基(NECナイメンヘン)をブレイクさせ、1年でJ2の2位へとチームをけん引し、J1昇格を掴んだのだ。
「彼は桐光学園からジュビロ磐田に入った頃からすごく期待された選手でした。だけど、思うように結果を出せず、たくさんの悔しさを味わい、崖っぷちに追い込まれていたと思うんです。
そういうタイミングで横浜FCに来て、『ここで活躍できなかったら選手として終わるかもしれない』という危機感を持ってサッカーに取り組んだ。2022年の航基は“選手として熟しきった状態”だったし、一番ハングリーになっている時期だったんです。
そんなときに、たまたま僕が立ち上げから攻撃的に行くという方向性を採ったので、彼がすごくマッチした。僕は『センターFWの選手は点を取ることに集中させたい』という考え方だったので、ポストプレーとか守備の部分は多少、目をつぶってでもペナルティーエリア内の仕事にフォーカスさせようとした。それで本人もストロングポイントが出しやすくなった。チームのやり方と航基のよさがマッチしたからこそ、得点を取り続けられたのかなと感じます」
四方田監督はそう述懐するが、確かに磐田時代の小川はチーム戦術とストロングがフィットしないケースが少なくなかった。水戸ホーリーホックにレンタルされた2019年後半は7点、磐田に戻ってきた2020年は9点と数字的に悪くない結果を残したこともあったが、長続きしない。絶対的エースとしてフル稼働したのは、四方田体制1年目の横浜FCが初めてだったのである。
「プロのステージで、フルシーズン戦うことの難しさを再認識し、どうやって結果を出していくのかを本人も真剣に考えたと思います。
2022年はサウロ・ミネイロ(現上海申花)、クレーべ、マルセロ・ヒアン(現FC東京)といったブラジル人FWもいましたし、日本人にも渡邊千真、伊藤翔とエース級になれる人材もいた。そういう陣容を踏まえて、航基に『シャドーでやってくれ』と注文すると、最初は『やりたくない』と拒否されました(苦笑)。
そこで『シャドーストライカーっていうイメージで構わない』と話したら、『その言い方が好きじゃないんで、ストライカーシャドーにしてください』と返された(笑)。やっぱり航基はストライカーに強いこだわりがあるんだなと痛感させられました。
結果的に両ポジションでいい働きをして、点を取れるところも見せてくれた。この経験は海外でプレーするようになった今の彼にとって、すごくいい学びになったのかなと感じます」
小川自身もさまざまな試行錯誤を繰り返したことで、現在のオランダでの活躍につながったのは確かだろう。
「僕はあまり言わなかったですけど、本人が『ポストプレーをもう少しよくしないといけない』とか『もっと前線から献身的に二度追いに行かなきゃいけない』という姿勢を示した通り、自分から足りないところをかなり意識したようで、トライ&エラーを繰り返していました。
今、日本代表で森保一監督からもそういう要求を当たり前のようにされていると思いますけど、FWとしての幅を広げていくことで、活躍の場が広がるのは事実なんです。
航基は横浜FCで自分なりに高みを追い求めた結果、『自分は点を取る部分で勝負していける』『ゴールを奪うことは誰にも負けない』という自信を得た。その力をJ1に上がった2023年前半にも示して、オランダ行きを勝ち取り、代表でも地位を築いた。昨年10・11月に日本代表で再会したときも成長を感じましたね」
教え子の前向きな変化を心から喜んでいる四方田監督。2026年北中米ワールドカップ(W杯)まであと半年。小川には上田綺世(フェイエノールト)と並ぶ日本のエースとして結果を出してもらう必要がある。四方田監督も大舞台で異彩を放つエースストライカーの姿を待ちわびているという。
「代表で練習している彼は、必死で生き残ろうという姿勢を前面に押し出し、守備のところも全力で最後まで追いかけていました。それをやらないとW杯に行けないと分かっているから、泥臭くしぶとくプレーしているんだなと感じました。
自分が関わった選手でもありますし、絶対にW杯に行ってほしいですし、結果を出してもらいたい。今の日本代表はうまく波に乗れれば上位進出も可能な力があると思うので、航基にはチームを引っ張っていってほしいと思います」
恩人の言葉を小川はどのように受け止めるのか。2026年のさらなる進化とゴール量産に期待したいものである。
(元川悦子 / Etsuko Motokawa)

元川悦子
もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。